大学院の魅力について
やっぱり大学院はレベルが高いと感じます。自分が知らないことを知れるし、専門性を持った人たちの話を聞けるのが本当に楽しいです。学部の時はどうしても授業の延長で話すことが中心でしたけど、大学院ではいろんな分野に興味を持つ人たちが集まっていて、それぞれが自分の専門を持っている。だから、自分にはない視点をどんどん吸収できるんです。
授業のスタイルも特徴的で、最初にレクチャーがあって、その後に「じゃあこれに対してどう考えるか」とディスカッションが始まる。あるいは、自分でテーマを持ってきて発表し、それに対する疑問点を投げかけてもらい、そこから議論を広げていく。そうすると、「あ、そんな見方があったんだ」という気づきが本当に多いんです。自分が発表するときも、自分はどうしても限られた視点から見てしまうんですけど、そこに新しい意見を与えてもらえるのが大きな魅力です。
さらに、先生との距離が近いのも大きな利点だと思います。先生の研究を手伝ったり、調査のお手伝いをしたりする機会があるんです。例えば、世界中の紛争に関する記事をリスト化して、内容や言及時期、誰が発言したのかなどを整理する作業を任されたこともありました。それだけでなく、先生が外部講師を呼んでシンポジウムを開くときに運営を手伝ったり、学会の案内が来るので自分が行きたい場所に参加できたりと、学問の現場に直接関われるのは大きな経験です。
院進学にあたって評価していただいたのは、自分の独自性です。特に、高校時代にGVで一緒に考えたこと、そして大学生活でさらに広げていった「スポーツ」というテーマは、自分にとってかなり特徴的な研究の軸になりました。そのおかげで大学院に進むことができたと感じています。
院進学にあたってはどういう対策?
自分の対策は、とにかく研究をひたすら極めることでした。文献を読むのはもちろん、考えを深めて先生とディスカッションを重ね、「こうじゃないか」「いや、こうじゃないか」という新しい視点をもらう。その視点をまた自分でブラッシュアップして、さらに違う本にあたる。そういう繰り返しで、本を読む量は本当に多かったです。もちろん過去問も解きますが、大学院に入って自分が研究したいものがなければ入る意味がないので、やはりそこを一番重視していました。
一次試験では分野ごとの大事な概念や考え方、最新の潮流について問われて、自分の場合は「人間の安全保障」という概念がテーマでした。今年でちょうど30年になるのですが、当時はスレブレニツァやルワンダのような内戦があり、とにかく緊急で人を守ることが第一の課題でした。しかし30年経った今では、世界中で武力紛争はそこまで多くはなく、むしろ人々の暮らしや経済、貧困といった領域にアプローチすることが中心になってきました。それが当時との大きな違いです。
ただ最近は再びガザやウクライナの問題が深刻化していて、人間の安全保障が対応できる範囲はやはり限られている、というのも大きな課題だと思います。そういう現実も踏まえたうえで、多角的に考えるためにはやはり本を読むことが欠かせません。
GVに通っていた頃は、先生方から自分の興味のある分野に関する本をたくさん紹介してもらいましたし、それについて意見を伝えるとさらに返答が返ってくる。そうやってキャッチボールができるのは本当に良い環境でした。学校の授業だと先生から教えてもらうだけになりがちですが、GVでは自分から投げかけ、それに対して返してもらえる。そこが大きな違いであり、研究姿勢を培う大切な経験になったと思います。
GVの学びは?
やっぱり一番学んだのは「教わりに行く姿勢」だったと思います。自分より知識を持っている人たちに対して、どういう質問をすればいいのか、どういう本を持っていけばいいのか――そういう基本的だけど大事なことをGVで学べたのは本当に大きかったです。
先生方は常に高い基準で問いかけをしてくれて、間違っていることや「もう少しこうしたらいい」ということを当たり前のように示してくれました。その基準に応えなければいけないという緊張感があって、それにどう努力していくかという姿勢がここで一番伸びた部分だと思います。特に推薦入試に向けた準備では、その経験が大きく活きました。
そして何より、先生との距離が近いというのは塾としての強みでした。すぐに相談できる環境があり、厳しさの中にも支えてもらえる距離感があったことは、自分にとってとてもありがたかったです。
今は学びの最高峰まで辿り着いたけど、何が支えになったか?
やっぱり一番大きいのは、自分の生まれ育った環境と、これまで生きてきた中で持ち続けてきた「軸」だと思います。それは結局「平和に対する感情」に繋がっています。
父は学者で、母は沖縄出身。母は平和に関するツアー活動に携わっていて、自分は3歳や4歳の頃からガマや平和記念公園などに足を運んでいました。そこで見たものは残酷で悲惨なものばかりで、「こうなってほしくない」という思いを幼いながら抱きました。現実に自分の周りは平和で、そのことに感謝しつつも「過去を背負わなければいけない」という感覚がずっと脳裏に残っていました。
10歳の時には海外で暮らす経験をしました。その中で「沖縄戦や第二次世界大戦のことをみんなに伝えたい」と強く思ったのを覚えています。アウシュビッツやノルマンディー上陸作戦の墓地を訪れ、戦争の悲惨さを肌で感じ、心にトラウマのように刻まれたものもあります。日本や沖縄、ドイツでは「敗戦国の歴史」を見てきましたが、イギリスに行って「戦勝国側の歴史」を目にした時には「勝ち負けではない。人が死んでいること自体が問題だ」と強く感じました。そこからさらに平和への思いは強くなっていきました。
イギリスでの生活ではサッカーとも出会いました。戦争の過去はあっても、今は一緒に笑いながらボールを蹴ることができる。その光景を見て「これが平和の理想の形だ」と心に刻まれた体験です。
自分の研究テーマを「沖縄戦」にしなかったのは、それを扱うとどうしても「歴史研究」になり、過去の教訓を与える形になるからです。それ自体はとても大切なことですが、すでに多くの人が取り組んでいる分野であり、また自分自身の祖先も亡くなっているため、感情的になってしまい客観性を保てないと感じました。研究論文として出すのは難しいと思ったんです。だからこそ、自分は「教訓を語る」のではなく、「これから実際にできること」に取り組みたいと考えました。そこで、自分が続けてきたサッカーやスポーツに可能性を見出しました。スポーツには人をつなぐ力があり、国連やヨーロッパでも「平和のためのスポーツ」が提唱されています。ここなら自分にも貢献できることがあるのでは、と感じています。
今「人間の安全保障」を学んでいて感じるのは、平和の形は時代によって変わってしまうということです。人間の安全保障が語る平和とは「武力紛争がない上で、人々一人ひとりの可能性が広がっていく状態」です。しかし現代の日本を見ると、紛争はなくても、貧困家庭や子どもの食事問題、経済不安といった現実がある。そう考えると「本当に土台はできているのか」と疑問を抱かざるを得ません。そういう現状を学べば学ぶほど、時には嫌になるくらいですが、それでも向き合うべき課題だと感じています。
先生の回想:受験当日エピソード
受験当日は直前までライン電話で面接練習をしていました。電車に乗るギリギリの瞬間まで対策を続け、「じゃあ行ってきます」と言って試験に向かったのを今でも覚えています。
試験が終わった直後、彼から届いた第一声は「先生、終わりました。いろんな意味で」というもの。詳しく聞くと、面接で「そんなの夢物語だよ」と言われたそうで、とても悔しさの残る試験だったと話していました。
ただ、その推薦入試で彼が描いたビジョンは、夢物語で終わらせないために、今も形にしようと挑戦し続けている。そう思うと、あの日のやり取りは今でも強く印象に残っています。


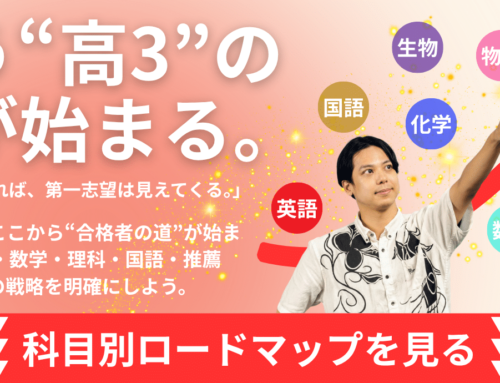

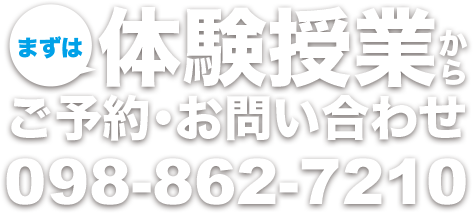

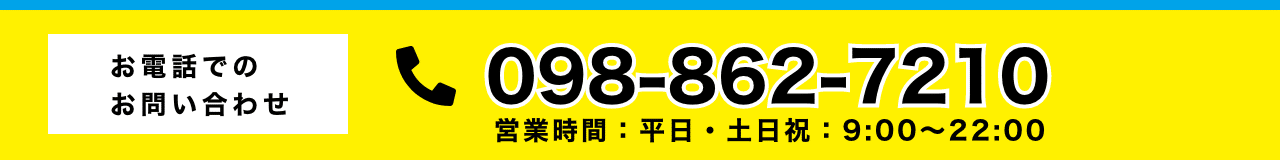


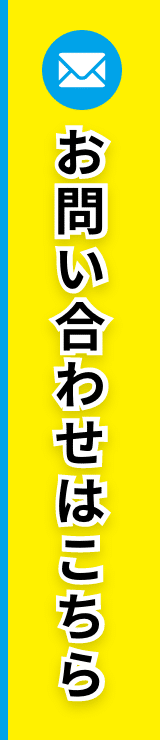
コメントする
You must be logged in to post a comment.