目次
💬 はじめに
「とにかく親に迷惑をかけたくない」「お金がかかるから言い出せない」
多くの生徒が抱える、そんな想いを乗り越えて——
今回は、実際にGVで生徒と向き合っているマネジメントスタッフの体験を通して、
“未来設計型マネジメント”のリアルな裏側に迫ります。
1.) 実際の高校1・2年生マネジメント事例
ある子は、最初に話をした時点で、すでに“名前を聞いたことがある大学”を志望校に挙げていました。ただ、話を深めていくうちに、「実は助産師になりたい」という思いがあることがわかってきました。
しかし、当初挙げていた大学の中には、助産師課程のカリキュラムがほとんどない大学もあり、
本人のやりたいことと進路が噛み合っていない状態だったんです。
そこで、「本当にやりたいのは何か?」という話から、職業を起点に大学を逆算して探していくマネジメントを始めました。数IIIや理科2科目など、当初考えていた進路はかなり要件が限定的だったため、
もっと選択肢を広げて、その子の目標に合った進路を描けるよう、志望校を再設計していきました。
そのうえで、「助産師になるために必要なカリキュラムが整っているかどうか」を軸に、大学を丁寧に絞り込んでいきました。
また、その子は英語に苦手意識があったので、英検の取得を目標に設定。
単語や文法などを「定期テストとは別軸で」集中して取り組めるようにし、
学習に小さな成功体験を積ませることを意識しました。
一方で、評定(内申点)も気にしていたため、定期テスト直前には、どの教科にどれだけ時間をかけるか、
点数の落ち込みやすい科目の優先順位付けなど、細かく学習配分を一緒に考えるようにしました。
このように、進路の軸と日々の勉強を結びつけながら、
「未来から逆算するマネジメント」を実践しています。
2.)自分が高校1〜2年のときにマネジメントがあったら
本当に、「あってほしかった」。その一言に尽きます。
当時の私は、受験について何も分からないまま、ただ「一発勝負だよ」「落ちたら浪人だよ」と言われ続けていました。
その言葉がずっと頭に残り、プレッシャーだけで勉強をしているような日々でした。
誰かに相談することもできず、勉強の進め方も見通しも分からない。
自分の中で「今これをやらなきゃ」という焦りだけが膨らんでいって、
視野が狭くなり、逆算もできず、気がついたら必要以上に自分を追い込んでいたと思います。
実際に、琉大の推薦の1週間前には、心も身体も限界で、「このままじゃダメだ」と思いながらもどうにもできなかったです。
そんな経験をして今、思うのは——
「月1のマネジメント=心の安全基地」になり得るということです。
それはただ学習管理をするだけではなく、“誰かと一緒に考えられる時間”があることそのものが、どれだけ心の支えになるか。
しかもそれが、先生のような「大人」ではなく、少し先を歩いている“先輩”だからこそ、伝わる言葉がある。
年齢も近く、同じ目線で話せる相手だからこそ、
「こうすればいいよ」と押しつけられるのではなく、
「分かるよ」と寄り添ってもらえることで、言葉の力がまっすぐ届く。
日々の学習や進路の悩みを、誰かと一緒に整理して言葉にできるだけでも、
あのときの自分にとっては、どれだけ救いになっただろう——と本当に感じます。
3.)進路が決まっていない子への関わり方
「進路が決まっていない自分はダメだ」と思い込んでしまう子は、本当に多いです。
実際、「自分だけ決まっていないのって、やばいですよね…」と、不安そうに口にする子もいます。
でも私は、たまたま医療に関わる経験が身近にあって、そこから自然と道が決まっただけなんです。
だから「決まっていないこと=悪いこと」では決してないし、それは本人のせいではありません。
むしろ、小・中・高とずっと5教科中心の勉強ばかりをしてきた中で、明確な将来像を持っているほうが珍しいと思っています。
だからこそ、最初に私が伝えるのは、
「やばくないよ」という、ほんの一言。
その言葉から、安心して話せる空気をつくることが、マネジメントの第一歩になります。
そのうえで、「好きなこと」「つい動いてしまうこと」「自然と興味を持っていること」など、
日常の中にある小さなヒントを一緒に拾い上げていきます。
必要に応じて、YouTubeなどの動画を送ることもあります。
少しでも「おもしろそう」「自分にもできるかも」と思えるきっかけを届けられたら、という思いで選んでいます。
また、「なぜその進路なの?」と聞いても、うまく答えられない子もいます。
そんなときは、一度立ち止まって、一緒に“言語化”の時間を持ちます。
それでも本人の意志が固いのであれば、そのまま進めばいい。
でも、もし迷っている様子が見えたら、選択肢を広げて再確認する、というアプローチを取るようにしています。
焦らず、でも確実に。
その子のペースで未来を探せるように——
そんなマネジメントを、いつも心がけています。
4.)マネジメントのやりがい
ある子のマネジメントを担当していたとき、面談の中でその子がしていた小さなミスやつまずきを、私は毎回メモに残していました。
読み間違い、計算ミス、時間配分のズレなど、「あのときこうすればよかった」という気づきが蓄積されていくような内容です。
共通テストが近づいてきた頃、ふと思ったんです。
「この子には、あのときの自分と同じ思いをしてほしくない」って。
実は私自身、受験本番でマークミスをしてしまい、本当に絶望的な気持ちを味わったことがありました。
それまでの努力が全部崩れてしまうんじゃないかと思うくらい、苦しかった経験です。
だからこそ、目の前の生徒には同じ思いをさせたくなくて、
これまで面談でその子がしていたミスや注意点を1枚の紙にまとめて、共通テスト前に渡しました。
「試験当日に、最後にこれを見て気をつけてほしい」——そんな想いを込めて。
すると後日、その子から「全部思い出して、絶対にミスしないように試験を受けられました」と連絡が届きました。
そのとき、自分の過去の失敗が、誰かの力になれたことに、あの経験が生きたと思えました。
マネジメントという立場で生徒に関わる中で、自分の経験が活かされていることが本当にうれしくて、
「やらなきゃ」じゃなくて、自然と「やりたい」と思えるようになったのも、この仕事のおかげだと感じています。
5.)マネジメントに込める想い
生徒が1時間、自分の時間を削って面談に来てくれる——
その1時間を絶対に無駄にしたくない。
面談の前には必ず準備をして、その子にとって意味のある時間になるよう心がけています。
というのも、自分自身にとっても、高校時代の1時間って本当に重たかったから。
切羽詰まっていたあの頃、1時間という時間の価値は、単なる60分以上のものでした。
「今この1時間、何をすべきか」「どう使えば結果につながるか」——
そんなことばかりを考えていたあの時期の感覚が、今も自分の中に残っています。
だから、生徒がわざわざ来てくれるこの時間を、ただの面談にしたくない。
志望校や進路、成績の状況、過去の面談記録や課題の進捗——
資料も送りますし、情報もできる限り整理しておきます。
本人が迷っていたり、気づけていないことを引き出すための問いかけも、しっかり考えておきます。
そして、たとえ進路がこの先変わったとしても、
「あの時の面談があったから、今の自分がある。」
そう思ってもらえるような関わりをしたい。
その気持ちを、ずっと大切にしています。
🚀 最後に:未来を一緒に描ける存在として
高校受験と違って、大学受験は「全国大会」です。
戦う相手は同級生だけではなく、全国の受験生や浪人生。
そして、その舞台に立つためには、今この瞬間からの積み重ねがすべてです。
だからこそ、部活も勉強も、定期テストも、すべてが未来に向けた“体力づくり”。
ただ頑張るだけじゃなく、「なぜやるのか」「どこにつながるのか」を一緒に見つけていくことが、私たちの役目です。
生徒がなかなか進路を見つけられず、迷っているとき、私自身も本当に苦しいです。
「どうしたら気づいてもらえるだろう」「何を届けたら動けるだろう」と悩み続ける日もあります。
でも、そんな日々を越えて、一緒にワクワクできたときの喜びは、すべてを超える。
これからも、悩んで、迷って、立ち止まる生徒たちに寄り添いながら、
一緒に考え、一緒に笑って、一緒に未来を描いていきたいと思っています。
🎬 追伸:マネジメントにも、いろんな色がある。
ここまで読んでくださって、ありがとうございました。
今回ご紹介したのは、あくまで“ひとつのマネジメントのかたち”。
GVには、他にもたくさんのマネジメントスタッフがいて、
それぞれが違う視点や関わり方で、生徒たちと向き合っています。
どのスタッフも、一人ひとりの「今」と「未来」に本気で向き合っているのは共通です。
だからこそ、誰と出会うか、どんな時間を過ごすかで、きっと見える景色が変わっていきます。
また別のスタッフのストーリーも、どうぞお楽しみに!



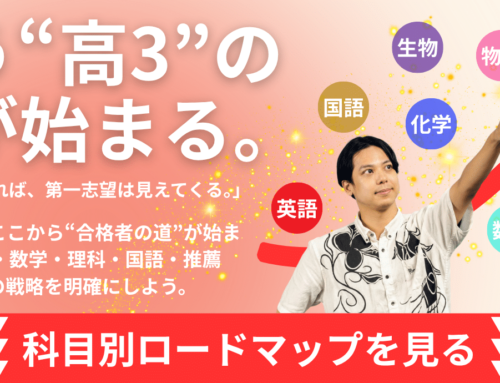

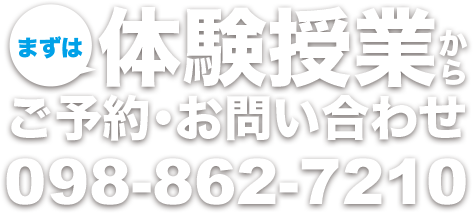

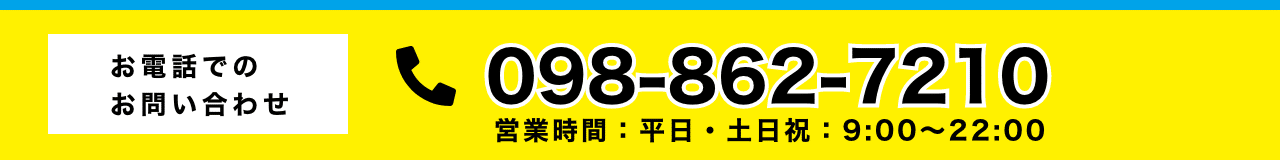


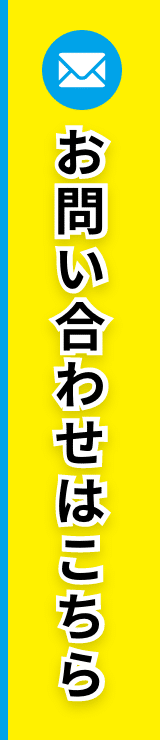
コメントする
You must be logged in to post a comment.