学問って、“大学へ行くこと”そのものじゃないんだ。
「自分の人生のリスクは、自分で取る」。
地方で生きる覚悟、そしてGVや家族の支え——。
高校生のあなたに。
⸻
Q1. 大学へ行って見えた“学問へのリスペクト”は?
僕が分かったのは、学問って「大学に行くこと」が目的じゃないってこと。
一番身が入るタイミングで、一番学びたいと思うものを学ぶとき、学問は本当の価値を発揮するんだ。
「とりあえず大学生になる」と決めて実現してみたけど、その後は混乱して必死にもがいて…。でもそこでようやく掴んだ感覚だった。
⸻
Q2. 一番大切にしている“舵の握り方”は?
「自分の人生のリスクは、自分で取る」。
大学を辞めると決めたとき、僕は“決めて立つ”って言葉どおりに舵を切った。自分で決めた瞬間から、嬉しさも悔しさも、自由も責任も、ぜんぶ自分のものになる。誰かに与えられた道じゃないし、流れで選んだ道でもないから、不満を人のせいにできないんだ。
「実は誰も決めてなくて、自分が決めてるはずなんだよね」。そう思うと納得できる。
もし転んでも「自分で選んだ」から悔いはない。
だから僕は、納得できないまま選ばない。お金だけじゃなく、環境も含めて自分で選んで、選んだ以上は自分で引き受ける。これは絶対に崩さない。
⸻
Q3. “地方創生”をどう捉えている?
外から来た人と、地元で生き続ける人。その間には必ず緊張感がある。
地元の人は「逃げ場がない」。一方で、外から来た人は「帰る場所がある」と思われる。僕自身も「お前には帰る場所があるだろ」と言われたことがある。
だからこそ思った。中途半端な気持ちで関わるのは失礼だ。ここでやるなら死ぬ気でやるしかない。
実際、この町には毎年200本もの視察が来る。でも本質はそこじゃない。
本質は「大切な人と日々をより良く暮らすこと」。
飲食店を作るのも、サービスを作るのも、ソフトを開発するのも、全部そのためなんだ。
引いて見ればそれが「地域おこし」と呼ばれるけど、僕にとってはシンプルに「自分と大切な人が豊かに暮らすこと」。それだけ。
⸻
Q4. 受験期の“分岐点”でGVはどう効いた?
もしGVがなかったら、正直僕は国外に逃げてたと思う。
高3の冬はボロボロで、海外留学の雑誌ばっかり見てた。
でも、GVの先生たちは本気で向き合ってくれたんだ。
金城先生は「海外に行くのもいい。でも日本の大学をちゃんと見てからでも遅くない」って言ってくれた。
そして大岩先生には本気で叱られた。あんなに本気で怒ってくれる大人がいたからこそ、僕は逃げずに大学を選べた。あれは本当に大きかった。
⸻
Q5. 「大学へ行く意味」そして「選び方」について
結果的に、大学へ行った意味は大きかった。学問としては違和感を覚えたけど、大学生活そのものには価値があった。
同じ立場で夢を語れる仲間に出会い、そこから休学や「夢を語れ」につながった。
大学に行ったからこそ「これは自分のやりたいことじゃない」って気づけたんだ。
だから僕は、目的から逆算して大学を選ぶべきだと思う。
見えないなら無理に選ばなくてもいい。
同い年でギャップイヤーをとって「本当にやりたいこと探し」をしていた友だちもいた。それも立派な選び方だ。
受験で大変なときほど、「自分の人生をかけて達成したいミッションは何か?」を忘れないでほしい。
⸻
Q6. 使命と、家族の支え
僕はずっと「生きてる意味」を考えてきた。見つからなければ「いなくてもいい」って思うタイプだった。
でも、アートを地域に落とし込む使命を見つけてからは、人生が大きく変わった。全部が「使命をどう遂行するか」で見えるようになった。
途中で「もう諦められたのかな」と思う時期もあったけど、結局、家族は僕の幸せを願って見守ってくれていた。
ただ黙って見守るって、実は一番むずかしい。心配を抱えながら任せてくれた親の大きさは、年を重ねるほどわかるんだ。だから今は心の底から感謝している。親は「帰る場所」以上の存在。挑戦を背中から押してくれる、目に見えない支えなんだ。
現在挑戦中のクラウドファンディングはこちらから


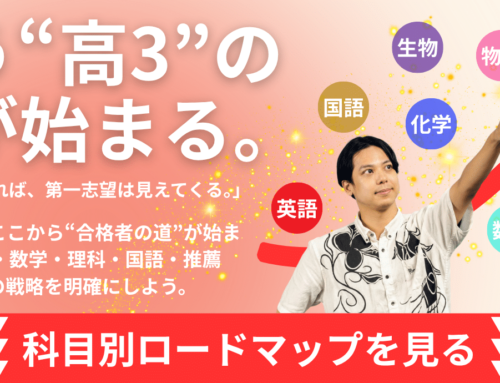

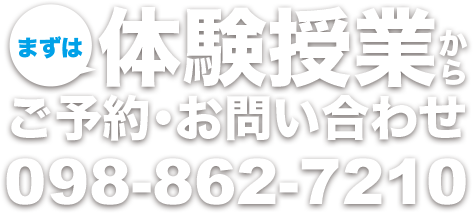

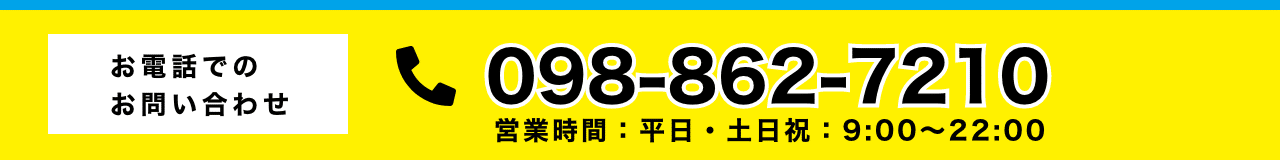


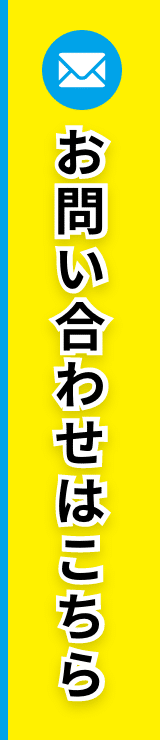
コメントする
You must be logged in to post a comment.