大学生活について
大学進学してまず実感したのは、「関わる人の数と幅が一気に広がった」ということでした。中国からの友達もいれば、岡山や大阪から来た友達もいる。高校までの人生では出会えなかった人たちと日常的に関わるようになり、自然と視野が広がっていきました。それぞれに「当たり前の人生」があって、自分とは違うけれど、確かにそこに存在している――その事実を知るだけで、世界が広がっていくようでした。私はまだ知らなかった「当たり前」がこんなにもあるのか、と。
同時に、大学に入ってからは「私って本当に非常識で、知らないことだらけなんだ」と実感する場面も多々ありました。推薦入試で先生と顔を合わせた時から、受け入れてくれた大学は一体私に何を期待してくれたのだろう、と考え続けていました。だって、あまりに話しやすい先生だったので、面接でうっかりタメ口をきいてしまったくらいの私なのに――。
やがて私が出した答えは、「人と違うことをしなさい」ということでした。卒業式の日、ちょうど学長が最後の挨拶をする場面に立ち会いました。AIが台頭してきた時代背景を語ったあと、「これからの時代、人間にできることとは何か、そして自分にできることとは何かを考えてほしい」と話されたのです。その言葉に、心から共感しました。実際には、その問いを私は大学生活の最初からずっと考えてきたように思います。授業を受けるときも常に「自分だったらどうするか」を真剣に考えていて、その分エネルギーを消耗することも多かったけれど、それが私にとって大切な姿勢でした。時にはサボってGoogleで調べてしまうこともあったけれど、結局それでは本当の学びにならないと気づき、地道に積み重ねました。その結果、成績も思いのほか良く、危なっかしかった私なりに、成長の伸びしろを掴めたのだと思います。
大学生活は、私にとって「学ぶことの楽しさ」を実感できた時間でした。とても充実していて、自分に合った選択だったと心から思います。音楽はずっと好きで、高校の時には芸大に進むか迷ったほど。でも、あの時芸大に行っていたら、今のような豊かさには触れられなかったはずです。音楽一本ではなく、いろんな人の話を聞き、フィールドワークで地域の人たちと関わる――役所の人や首里の屋台の人にまで話を聞く機会がありました。さらにアルバイトもいくつも経験し、多様な立場を知ることができた。その積み重ねが、私の人生をとても豊かにしてくれました。
大学で広げた視野があるからこそ、これから向き合う音楽にも厚みが出るのだと思います。音楽をもっと深く理解し、詩を書き、表現を極めていく。その出し方を磨いていくことが、今の私の使命です。若いうちに多くの「いいもの」に触れておきたい。大学で培った学びと経験を、今後は音楽を通して外へと手放し、届けていきたい――そう強く思っています。
大学生活を休学した理由
私は人生を振り返ってみても、ずっと“とんとん拍子”だったんです。小学校、いや、それどころか保育園、幼稚園、学童から始まって、小学校、中学校、高校、大学と――進級、進学、進級、進学。その流れが一度も途切れず続いてきて、止まることもなく走ってきた。ありがたいことではあるけれど、逆に「これでいいのか」と疑問が芽生えていました。
そして就活が始まったときに、強烈な違和感を覚えたんです。まるで船に乗って川に流されていくみたいに、ただ時の流れに押されて進んでいる感覚。これは危ういなと思った。失敗して止まるか、自分で止めるしかない。そう気づいたとき、「じゃあ自分で止めよう」と決意したんです。だから休学を選びました。流れを断ち切り、立ち止まって考える。その時間が必要でした。
そのきっかけの一つが、大学の講義でやった「就活プログラム」でした。企業の人が来て、大教室で「エキサイティングなゲームをしましょう」と言う。お金を増やすゲーム。4人グループで戦略を立てて物を売り、持ち金を増やしていく。確かに楽しかった。仲間と笑い合って「増えないじゃん!」と盛り上がった。けれど、ふと我に返った瞬間があったんです。――あれ、これが“社会人になること”? これをうまくやることが就職? その瞬間、吐き気がこみ上げてきました。社会の仕組みに組み込まれていく自分を想像しただけで、身体が拒否反応を示したんです。実際に講義を途中で抜け出すほどに。「ああ、私は“企業に就職する”という道は嫌だ」――そうはっきり思ったのは、まさにその時でした。
2年後半でその思いは固まり、3年に入ると「じゃあ自分はどうする?」という問いに直面します。周りは次々と内定を決めていく。焦りの中で自分に残された道を考えたとき、心の底から出てきたのは「音楽をやりたい」という思いでした。ただし中途半端にやるのではなく、本気で、無理だと思うところまで突き詰めたい。その覚悟を持って、3年後半に休学を決意しました。
東京に行ったのは、トップレベルの人たちに出会える場所だから。とにかく一流の音楽を聴き、一流の人たちの話を聞き、すごいものを目で見ておきたい。その直感で動いたんです。結果的に、その選択は大正解でした。東京で2度ライブをし、観客の反応を肌で感じて、「あ、いける。私は音楽でやっていける」と確信を持つことができたからです。
音楽活動について
沖縄に帰ってくる少し前、2〜3ヶ月前くらいのことでした。これまで出演したことのある沖縄のイベント関係者から連絡をいただいたんです。「こんなチームがあって、女性ボーカルを探しているんだけど、あいりどうかな?」と。そこでまずはそのグループの音楽を聴いてみたら――もう一発で「めっちゃいい!」となりました。しかもメンバー全員がうるま市出身の仲間たち。
とりあえず最初はコラボという形で関わることになり、1曲目として Beat of the Soul がリリースされました。そのとき私はチームメンバーではなく、“featuring ナカザアイリ” という形での参加。でもその制作がものすごく楽しくて。ずっと一人で孤独に音楽をやってきたからこそ、「チームで作業するってこんなに楽しいんだ」と心から感じた瞬間でした。当時は東京でレコーディングしていて、やり取りは電話やビデオ通話だけでしたが、それでも強い仲間意識が生まれたんです。「この人たちを信じよう」と自然に思えました。
そして沖縄に戻ってからは、ほぼ毎日のように顔を合わせて制作しています。この仲間たちとなら、これからさらに飛躍していけるんじゃないか――そんな期待も感じています。
GVをなぜ信じられたのか
最初にGVを訪れたとき、まだ机もなく、写真に映る建物も正直「大丈夫かな」と思うほどだった。私は何でもかんでも信じる性格ではなく、疑う目も持っている。けれどGVは、最初から「一人ひとりを見よう」としていた。
どこの塾も電話対応から始まる。だからGVに連絡した時も「どんな言葉で話すのだろう」と耳を傾けた。無意識にも、相手の声や言葉遣いからその塾の姿勢を感じ取ってしまうものだ。GVは事務的ではなかった。対応してくれた人も「どんな子なのか」を知ろうと、質問を投げかけてくれた。その温かさに、廃墟のような見た目とのギャップを感じつつ、安心感を覚えた。実際に行ってみても、みんなが温かかった。
他の塾も見学した上で、やっぱり「ここだ」と決めた。見栄を張らず、形から入らない姿勢。外観は更新されず、Googleの写真も廃墟のままだったけれど、内側を何とかしようとする熱意が伝わってきた。今振り返ると、その素朴さに強く惹かれたのだと思う。
勉強環境も整っていて、先生たちは大量の紙を使って資料集を作ってくれた。学びやすさは抜群だった。高校生の頃の私は、目の前に「いいかも」と思えるものが現れれば、とにかくしがみついていた。ただ、そこにいる人が優しそうで、信じられる存在であったことが決め手だった。
GVのためだったら何でもすると思えた理由
家庭の事情もあり、不安定な時期が多かった私にとって、GVは「寄り添ってくれる居場所」になった。学校が終われば自然と足が向き、ルーティーンのように通った。多感な時期に、ただひたすら個人を応援してくれる場所は必要だったし、私だけでなく他の生徒にとってもそうだったと思う。
だからこそ、早く恩返しをしたいと心から思っている。GVには、それほどの恩を感じている。もちろん「居場所」であるだけではなかった。先生たちの授業は分かりやすく、学びに夢中になれた。もしその部分が微妙だったら、きっとここまで熱中できなかっただろう。
GVでは、知識だけでなく「こういう考え方もある」という新しい視点をたくさん教えてもらった。大学で初めて触れていたら戸惑ったかもしれないことを、高校時代に準備できたのは大きかった。体系的な学びだけでなく、余談や雑談にも付き合ってくれる懐の深さがあって、そこから得た学びも数えきれない。
GVとはどんな場所だったのか
GVは、日々「学ぶことの楽しさ」を教えてくれる場所だった。そして大学に進学したことも、私にとっては大正解だった。できれば少し背伸びして入学し、自分の器を広げることが大切だと思う。その器の大きさが、今後の人生でどんなことがあっても受け止められる自分を作ってくれた――GVはまさに、そんな「自分を育ててくれた場所」だった。
大学生活の4年間、ずっと同じ場所に居続けるのは長い。だから私は休学を選んだし、友達は交換留学でハワイやオーストラリアに飛び出していた。どんな形であれ、一度外の世界に出てみることは必要だと思う。GVで学んだ「学ぶ楽しさ」と「挑戦する勇気」が、その後の大学生活をより豊かにしてくれた。
今後の目標
私の目標は、世界に挑むことです。まだ見ぬもの、未知のものに出会い続けたい。そのたびに驚き、学び、吸収し、自分という存在をどんどん大きく育てていきたいんです。世界を目指すことは、決してゴールではなく、さらに新しい世界へつながる入口だと思っています。そこにある音楽、人々、文化、すべてを取り入れて、自分の表現に変えていく。その果てにどんな景色が待っているのか、私は楽しみで仕方がありません。
だからこそ、これからも私は挑み続けます。世界のどこにいても、「音楽を信じる」と決めた自分で。


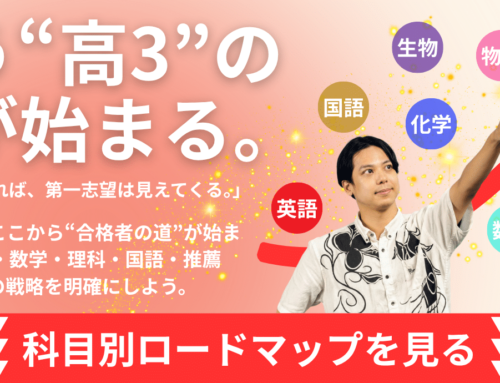

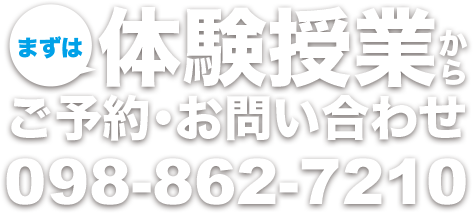

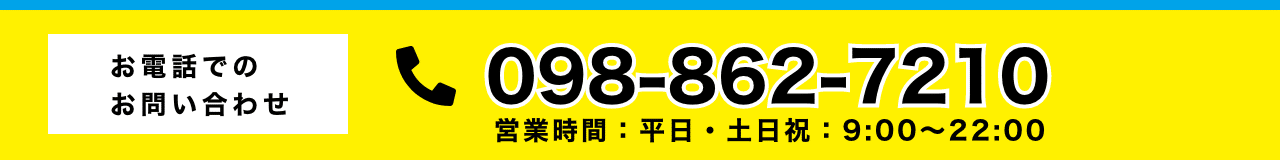


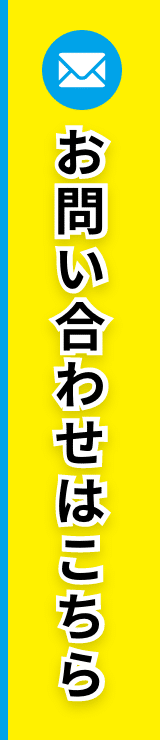
コメントする
You must be logged in to post a comment.