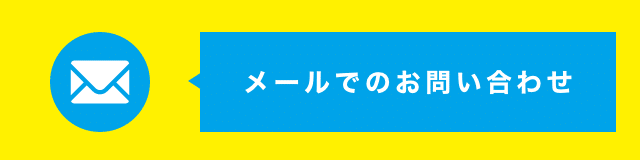〈本文理解〉
出典は谷川俊太郎『詩を考える〜言葉が生まれる現場』。
関連 2020京大国語/第二問/大岡信・谷川俊太郎『詩の誕生』↓↓
https://note.com/pinkmoon721/n/n43989d3a0b3e
関連 2010東大国語/第四問/小野十三郎「想像力」↓↓
https://note.com/pinkmoon721/n/n11967862be75
〈本文理解〉
①段落。「あなたが何を考えているのか知りたい」小田久郎さんはそうおっしゃった。電話口を通してぼそぼそと響いてきたその肉声だけが、私にとってこんな文章を綴ろうとする唯一の理由だと、そんなふうに私は感じている。
②段落。編集者である小田さんの背後に、無限定な読者を想定することは、今の私にはむずかしい。私の書くことはみな、まったく私的なことで、それを公表する理由がどこにあるのか見当がつかない。それでも私は電話口で小田さんの肉声に自分の肉声でためらいながらも答えたのである。
③段落。原稿をひきうけるという一種の商取引に私たち物書きは慣れ、その行為の意味を深く問いつめる余裕を持てないでいるけれど、その源にそんな肉声の変換があるとするならば、それを信じてみるのもいいだろう。
④段落。作品をつくること(詩、歌、子どもの絵本など)と、このような文章を書くことの間には、私にとっては相当の距離がある。
⑤段落。「作品をつくっているとき、私はある程度まで私自身から自由であるような気がする」(傍線部ア)。自分についての反省は、作品をつくっている段階では、いわば下層に沈殿していて、よかれあしかれ私は自分を濾過して生成してきたある公的なものにかかわっている。私はそこでは自分を私的と感ずることはなくて、むしろ自分を無名とすら考えていることができるのであって、そこに私にとって第一義的な言語世界が立ち現れてくると言ってもいいであろう。
⑥段落。私には作品と文章のちがいは、少なくとも私自身の書く意識の上では判然と分かれている。その意識のうえでの差異が、私に詩のおぼろげな輪郭を他のものを包みこんだ形で少しでもあきらかにしてくれていることは否めない。
⑦段落。…作品においては無名であることが許されると感じる私の感じかたの奥には、詩人とは自己を超えた何ものかに声をかす存在であるという、いわば媒介者としての詩人の姿が影を落としているかもしれないが、そういう考えかたが先行したのではなく、言語を扱う過程で自然にそういう状態になってきたのだということが、私の場合には言える。
⑧段落。真の媒介者となるためには、その言語を話す民族の経験の総体を自己のうちにとりこみ、なおかつその自己の一端がある超越者(…もしかすると人類の未来そのものかもしれない)に向かって予見的に開かれていることが必要で、作品をつくっているときの自分の発語の根が、こういう文章ではとらえきれないアモルフな(→注:一定の形を持たない)自己の根源性(オリジナリティ)に根ざしているということは言えて、「そこで私が最も深く他者と結ばれている」(傍線部イ)と私は信じざるを得ないのだ。
⑨段落。そういう根源性から書いていると信ずることが、私にある安心感を与える。これは私がこういう文章を書いているときの不安感と対照的なものだ。自分の書きものに対する責任のとりかたというものが、作品の場合と、文章の場合とでははっきりちがう。
⑩段落。作品に関しては、そこに書かれている言語の正邪真偽に直接責任をとる必要はないと私は感じている。美醜にさえ責任のとりようはなく、私が責任を取り得るのはせいぜい上手下手に関してくらいなものだ。創作における言語とは本来そのようなものだと、個人的に私はそう思っている。…
11段落。逆に言えばそのような形で言語世界を成立させ得たとき、それは作品の名に値するので、現実には作家も詩人も、創作者としての一面のみでなく、ある時代、ある社会の一員である俗人としての面を持つものだから、彼の発言と作品とを区別することは、とくに同時代者の場合、困難だろうし、それを切り離して評価するのが正しいかどうか確言する自信もないけれど、離れた時代の優れた作品を見るとき、あらゆる社会条件にもかかわらずその作品に時代を超えてある力を与えているひとつの契機として、「そのような作品の成り立ちかた」(傍線部ウ)を発見することができよう。
12段落。〈作品〉と〈文章〉の対比を、言語論的に記述する能力は私にはない。私はただ一種の貧しい体験談のような形で、たどたどしく書いてゆくしかないので、初めに述べた私のこういう文章を書くことへのためらいもそこにある。「作品を書くときには、ほとんど盲目的に信じている自己の発語の根を、文章を書くとき私は見失う」。作品を書くとき、私は他者にむしろ非論理的な深みで賭けざるを得ないが、文章を書くときには自分と他者を結ぶ論理を計算ずくでつかまなければならない。
13段落。どんなに冷静に言葉を綴っていても、作品をつくっている私の中には、何かしら呪術的な力が働いているように思う。この力は下の方から持続的に私をとらえる。それは日本語という言語共同体の中に内在している力であり、私の根源性はそこに含まれていて、それが私の発語の根の土壌となっているのだ。
問一「作品をつくっているとき、私はある程度まで私自身から自由であるような気がする」とあるが、それはなぜか、説明せよ。(60字程度)
理由説明問題。本文は、詩人である筆者が「作品」をつくることと、一般の「文章」を書くことを対比しながら、本文の中盤で前者について考察し、それを挟む冒頭(①〜③)と結部(12)で後者の困難さを述べるという構成になっている。この対比を踏まえ、理由の終点「私自身から自由である」に着地する、「作品」つくることの性格をまとめればよい。
根拠としては、傍線のある⑤段落「(作品をつくる段階では)自分を無名とすら考えている」を手がかりに、⑦段落「無名であることが許されると感じる私の感じかたの奥には、詩人とは自己を超えた何ものかに声をかす存在であるという、いわば媒介者としての詩人の姿が影を落としているかもしれない」を拾えばよい。加えて、「文章」について述べた②段落「無限定な読者を想定することは、今の私にはむずかしい」を踏まえ、逆に「作品」は「無限定な読者に向けて(無理なく)提示される」ものである(自明ではあるが)。解答は「無限定な読者に作品(→創作物)を提示→自己を超える何かを声と言葉で媒介する→自己は無に帰す(よって私自身から自由)」とまとめる。
〈GV解答例〉
詩人である筆者にとって無限定な読者に向かい創作物を提示することは、自己を超える何かを声と言葉で媒介することで、自己は無に帰すから。(65)
〈参考 S台解答例〉
作品とは、特定の現実を生きる自己から離れ、個を超えたものに身を委ねることでおのずと生成してくる言語世界であるから。(57)
〈参考 K塾解答例〉
作品をつくるときには、一個人として言葉を紡ごうとする意識は影を潜めていき、言語共同体に立脚した無名性を感じさせる言葉が立ち現れるから。(67)
〈参考 Yゼミ解答例〉
作品をつくる時、作者は日本語という言語共同体に内在する力を感じ、自身の根源にある言語に触れることで私的な自己から解放されるから。(64)
〈参考 T進解答例〉
作品は、日本語という言語共同体に内在する力の働きに捉えられた自己が、自然に無名の存在と化していくなかで立ち現れる言語世界から生み出されるものだから。(74)
問二「そこで私が最も深く他者と結ばれている」とはどういうことか、説明せよ。(60字程度)
内容説明問題。「そこ」と「…他者と結ばれている」を具体化すればよい。「そこ」は前文の「アモフルな自己の根源性」「作品をつくっているときの自分の発語の根」(A)と対応する。さらにAは、その前文「その言語を話す民族の経験の総体を自己のうちにとりこみ」(B)、「自己の一端がある超越者(…人類の未来そのものかもしれない)に向かって予見的に開かれている」(C)場である。Cが分かりにくいが11段落の内容「ある時代背景で生まれた作品が、やがて時代を超えた力をもちうる」を踏まえ、「そこ」を「自己の言語共同体の経験の総体をとりこみ(B)/普遍の表現に向かって(C)/言葉を発する地点(A)」とした。
では、「そこ」で「…他者と結ばれている」とはどういうことか。ここは本文の根本的な理解に関わるところで、特に結部「作品を書くとき、わたしは他者に…非論理的深みで賭けざるを得ない」(12)、「(私を下の方から持続的にとらえるのは)言語共同体の中に内在している力であり、私の根源性はそこに含まれていて、それが私の発語の根の土壌となっている」(13)を参照するとよい。つまり、「そこ」は主客未分で形を取る前の(←アモフルな)、自己が意識される前の根源的な境地(西田幾多郎の「純粋経験」に相当するもの)であろう。「〜地点において〜自他が未分で不定形の根源性があるということ」とまとめる。
〈GV解答例〉
自己の言語共同体の経験の総体をとりこみ、普遍の表現に向かって言葉を発する地点において、自他が未分で不定形の根源性があるということ。(65)
〈参考 S台解答例〉
創作時の発語が言語共同体の経験の総体に根ざしたものとなることで、他者との根源的なつながりが実感されるということ。(56)
〈参考 K塾解答例〉
不定形な自己の根源性に根ざして、自己を超えた何かを媒介する創作者は、同じ言語を話す人々と歴史的にも予見的にも総体として深く結びつくということ。(71)
〈参考 Yゼミ解答例〉
自己を超えた存在の媒介者として創作する時、自身の存在の根底にある民族の経験の総体に触れることによって他者と深くつながるということ。(65)
〈参考 T進解答例〉
超越者を媒介すべく内在化される言語共同体の経験の総体に通じ、発語の源であると作者が信じる、不定形な自己の根源という深部で、他者とつながるということ。(74)
問三「そのような作品の成り立ちかた」とはどういうことか、説明せよ。(60字程度)
内容説明問題。「そのような」の指す内容が捉えづらいが、いったん前後のつながりの中に戻して、指示内容を改めて検討してみる。すると「離れた時代の優れた作品を見るとき/…その作品に時代を超えてある力を与えているひとつの契機として/(傍線部)/を発見することができよう」と整理できる。つまり「時代を経て普遍的な魅力を持ち得た作品(A)/の契機となった「作品の成り立ちかた」」を問うているのである。
そこでAに至る前、作品はどのように成立したかを、傍線より前にたどってまとめると、「ある時代、ある社会の一員であった作者が(11)/発語の根であるアモルフな自己の根源性から(⑧⑨)(C)/言語世界として引き出し(←媒介⑦)成立させたもの(11)」(B)となる。解答は「Aも、元はB」という形にする。Cの部分は問二ですでに説明したので、簡潔に「対象から」とした。
なお、⑩段落の「作品に対して作者には責任がない」という内容は、⑦〜⑨段落の「作品に対する媒介者としての作者の役割」(作品の成り立ちかた)から導かれる補足事項である。よって、解答に盛り込む必然性はない。
〈GV解答例〉
時代を経て作者から離れ普遍性を獲得した作品も、元は特定の時代と社会に生きる作者が対象から言語世界として引き出したものだということ。(65)
〈参考 S台解答例〉
作品は、社会の一員としての自らの言葉の意味や価値への責任から切り離されたところで、普遍的なものとして立ち現れてくること。(60)
〈参考 K塾解答例〉
特定の社会に帰属し、創作者でも読者でもある立場でもある人物を通して、言語共同体に内在する力が導き出され、人々と広く共有される作品が成立すること。(72)
〈参考 Yゼミ解答例〉
作品が時代を超えた普遍的な力をもつために、創作時に作者が創作者であると同時に、同時代の読者であるという言語世界が成立していること。(65)
〈参考 T進解答例〉
作者が、内容の真偽についての責任など一切取らず、言語共同体に内在する力が働く自己の根源性に根ざして創作することで成立し得た言語世界であるということ。(74)
問四「作品を書くときには、ほとんど盲目的に信じている自己の発語の根を、文章を書くとき私は見失う」それはなぜか。(60字程度)
理由説明問題。本問も、問二と同じく、本文の根本理解に関わる問題で、「作品」について問うた問二に対して、その裏にあたる「文章」について問う問題である。よって、本文の結部にあたる12段落(「文章」)と13段落(「作品」)を参照する。特に、傍線直後「作品を書くとき、私は他者に…非論理的な深みで賭けざるを得ないが/文章を書くときには自分と他者を結ぶ論理を計算ずくでつかまなければならない」(A)の解釈がポイントとなる。
そこで、裏の「作品」(13)から考えると、その「発語の根の土壌/根源性」には「下のほうから持続的に私(→作者)をとらえる/何かしら呪術的な/言語共同体の中に内在している力」があった。ここからAを解釈すると「作品」において作者は自他が未分の状態(←「民族の経験の総体」⑧)に発語を委ねることができるが、「文章」においてはその「根」に委ねることが許されず、自他を分離して自己の輪郭を明確にした上で、自他に通じる論理を駆使して他者に伝える必要に迫られる、ということになるのではないか。この後半の内容が解答の核となる。こう考えることで、本文冒頭(①〜③)の「文章」を書くことの苦悩(そのためには明確な他者を想定しなければならない)や、⑧段落「作品/安心感」「文章/不安感」の内容も自然と理解できるだろう。
〈GV解答例〉
自己を表現する文章では、作品の発語を生み出す根源から自他を切り分けた上で、対象化した自己を論理的に他者へと架橋する必要があるから。(65)
〈参考 S台解答例〉
文章で自分の考えを伝える際は、意識が自己へ向かい、他者との根源的なつながりが絶たれてその間隙を論理で埋めることになるから。(61)
〈参考 K塾解答例〉
作品を書く行為は言語共同体に内在する根源的な力に根ざしているが、私的な文章を書くときには他者に通じる論理を自分自身で見出す必要があるから。(69)
〈参考 Yゼミ解答例〉
作品の創作ではその言語を使う民族の経験の総体に身を委ねることができるが、文章では個として読者に論理的に説明するしか方法がないから。(65)
〈参考 T進解答例〉
文章で自分の考えを書く際には、自分の根源性を含む言語共同体に内在する力を排し、私的存在たる自分を内省した上で、他者に通じる論理を探さねばならないから。(75)