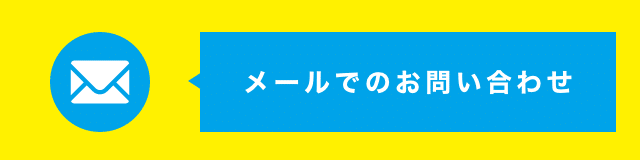〈本文理解〉
出展は藤原新也「ある風来猫の短い生涯について」。
①~④段落。南房総の山中の家には毎年天井裏で子猫を産む多産猫がいる。私の知る限りかれこれ総四、五十匹産んでいるのではなかろうか。猫の子というよりはまるでメンタイコのようである。そういった子猫たちは生まれてからどうなったかというと、このあたりの猫はまだ野生の掟や本能のようなものが残っていて、ある一定の時期が来ると、とつぜん親が子供が甘えるのを拒否しはじめる。親から拒絶されて行き場のなくなった直後の子猫というものは不安な心許ない表情を浮かべ、痛々しさを禁じえないが、これがいざ自立を決心したとき、その表情が一変するのに驚かされる。徐々にではなくある日急変するのである。それから何日かのちのこと、不意に姿を消している。帰ってくることはまずない。一体それが何処に行ったのか、私はしばしば想像してみるのだが、こころ寂しい半面「なにか悠久の安堵感のようなものに打たれる」(傍線部ア)。見事な親離れだと思う。親も見事であれば子も見事である。子離れ、親離れのうまくいかない人間に見せてやりたいくらいだ。
⑤~⑬段落。かえりみるに、それらの猫に餌をやったという経験は一度しかない。釣ってきた魚をつい与えてしまい、その猫が餌づいてしまったのである。しかしその猫も野生の血が居残っていると見え、ある年の春不意に姿を消した。それ以降私は野良猫には餌をやらないことにしている。これらの猫は都会の猫と違って自然と一体化したかたちで彼らの世界で自立していると思っているからだ。自分の気まぐれと楽しみで猫の世界に介入することによって猫の生き方のシステムが変形していくことがあるとすれば、それは避けなければならない。
ところが私は再びへまをした。「死ぬべき猫を生かしてしまったのだ」(傍線部イ)。二年前の春のことである。生まれて一年になる四匹の子猫のうちの一匹が死にそうになったときのことである。
遅咲きの水仙がずいぶん咲いたので、それを親戚に送ろうと思い、刈り取って金盥に生かしていた。朝刈り取り、昼に何気なく窓から目をやったとき、一匹の野良猫が一心にその水を飲んでいる姿が見えた。外見的にはあきらかに病気持ちである。(中略)。一年も生きているのが不思議なくらい、この子猫はあらゆる病気を抱え込んでいるように見えた。しかしそれも宿命であり、野生の掟に従ってこの猫は短い寿命を与えられているわけだから、私がそれに手を貸すのはよくないことだと思い、そのまま生きるようにさせておいた。
この猫が一心に盥の水を飲んでいたわけだが、飲んでから、四、五分たったときのことである。七転八倒悶えはじめた。(中略)。ひょっとしたら、と思う。あの水は有毒なものに変化していたのかも知れないと。(中略)。私は猫の苦しむ様子をみながら、間接的にそのような苦しみを私が与えたような気持ちに陥った。
そのような経緯で私はつい猫を家に入れてしまったのである。せめて虫の息の間だけでも快適にさせてやりたかったのである。
⑭~⑲段落。ところが、この病猫、元来が病持ちであるがゆえにしぶといというか、再び息を吹き返したのである。そしてそのまま家に居着いてしまった。このそんなに寿命の長そうではない病猫につい同情してしまったのが運のつきである。ときに人がやってきたとき、家の中にあまり芳しくない臭気を漂わせながら、あたりかまわずよだれを垂らし、手からは血膿の判子を押してまわるこの痩せ猫を見てよくこんなものの面倒をみているなぁとだいたい感心する。その感心の中にはときには私のボランティア精神に対する共感の意味も含まれているわけだが、「私はそれはそういうことではない、と薄々感じはじめていた」(傍線部ウ)。
人間にかぎらず、およそ生き物というものはエゴイズムに支えられて生きながらえていると言っても過言ではない。無償の愛という言葉があるが、そこに生き物の関係性が存在するかぎり完璧な無償というものはなかなか存在しがたい。(自己を犠牲に他者を救い命を落としたクリスティアンの逸話/そこにも教義に従うという冥利がある)。
そういうものと比較するのは少しレベルが違うが、私が病気の猫を飼いつづけたのは他人が思うように自分に慈悲心があるからではなく、その猫の存在によって人間なら誰の中にも眠っている慈悲の気持ちが引き出されたからである。つまり逆に考えればその猫は自ら病むという犠牲を払って、他者に慈悲の心を与えてくれたということだ。誰が見ても汚く臭いという生き物が、他のどの生き物よりも可愛いと思い始めるのは、その二者の関係の中にそういった輻輳した契約が結ばれるからである。
この猫は、それから二年間を生き、つい最近、眠るように息をひきとった。死ぬと同時に、あの肉の腐りかけたような臭気が消えたのだが、誰もが不快だと思う臭気がなくなったとき、「不意にその臭いのことが愛しく思い出されるから不思議なものである」(傍線部エ)。(了)
──私たち人間は、ふとした時に自然の営みに触れ─それは時に悲惨な状況をもたらす─それに畏れを抱く。しかし人間の営みも、ちっぽけかもしれないが、捨てたもんじゃない。
〈設問解説〉問一「なにか悠久の安堵感のようなものに打たれる」(傍線部ア)とあるが、どういうことか、説明せよ。(60字程度)
内容説明問題。「Aに/悠久の/安らぎを覚える」とする。Aを具体化した上で、「安らぎ」につながる「悠久」さについて考える。Aは直接的には「子猫の自立(③)」だが、その前提として「親猫の拒絶(②)」も加える。その「拒絶」は「とつぜん(②)」やってくるものであり、それは「野生の掟や本能(②)」を思わせるものである。これは「子猫」の方も同じで、「急変(③)」であり、「野生の血(⑤)」を感じさせるのである。
「親猫の拒絶/子猫の自立は/ともに急にくるものであり/野生の掟や本能を感じさせる」、これが、どう「悠久の安堵感」につながるのか。直接的に言及している箇所はない。つまり「自明」とされているのだ。すべてを述べるのは野暮である。その「自明」を復元する力を読者は、そして解答者は求められているのだ。
多産猫は、子猫がある程度まで育てば、また次の生殖に備えなければならない。いつまでも子猫がいるのは邪魔である。子猫も方も、親から別れて、それぞれの場所で新たな営みをもつだろう。そして生命の営みは強靭に継続する。そこに人間的な情を差し挟む余地などない。そうした野生の悠久の営みに、やはり生命の欠片である人間は、畏れながらも安らぎを見出すのである。
<GV解答例>
親猫がある時急に子猫を切り離し、子猫もある日自立を決心し親元を去る姿に、生命を繋いできた野生の本能を見、安らぎを覚えるということ。(65)
<参考 S台解答例>
親猫の拒絶に応じ決然と自立する子猫の姿には、人間が見失った自然の摂理に従う生命の爽やかな厳しさが感じられるということ。(59)
<参考 K塾解答例>
親に拒絶され、野生の掟に従って健気に自立し、遥かに続く自然の営みと一体化していく子猫たちの運命を想像して、深い安らぎと感動を覚えるということ。(71)
<参考 T進解答例>
親から拒絶された不安を乗り越え、見事に親離れして姿を消した子猫のことを想像すると、野生の掟に従う、時を越えた確かな持続が実感されて、感銘を受けたということ。(78w)
問二「死ぬべき猫を生かしてしまったのだ」(傍線部イ)とあるが、どういうことか、説明せよ。(60字程度)
内容説明問題。「しまった」とは、何か失態をやらかした、ということである。「死ぬべき猫を生かした」のは、前⑤段落「自然と一体化した/猫の生き方のシステム」への不当な介入である。その「システム」では、この弱った病猫が死ぬのは「宿命(⑩)」であり、「自然の掟にしたがう(⑩)」ことである。つまり、自然淘汰の摂理である。
筆者は、自分が置いた盥の水を飲んだ後、悶え苦しむ病猫を見て、間接的に自分がその苦しみを与えたような気持ちになる(⑫)。その自責と同情(⑭)から、個体を淘汰しながら種を繋ぐ自然の摂理に反して、筆者はその猫を生かしてしまった、のである。
<GV解答例>
自分が置いた盥の水を飲んだ後で悶える病猫に自責と同情を覚え、生命を淘汰しながら繋ぐ自然の摂理に反してその猫の命を延べたということ。(65)
<参考 S台解答例>
病む猫の壮絶な苦しみへの自責の念から、自然と一体化した猫の世界に不用意に介入し、その生をゆがめてしまったということ。(58)
<参考 K塾解答例>
猫の世界に介入すべきではないと思いつつ、自然の摂理に従えば死ぬはずだった猫を、間接的に苦しみを与えたとする罪悪感から、助けてしまったということ。(72)
<参考 T進解答例>
病んで短命だったはずの猫の苦しみに間接的な責任を感じてつい世話をして生き長らえさせ、自然と一体化した野生動物の世界に介入するという失態を犯したこと。(74)
問三「私はそれはそういうことではない、と薄々感じはじめていた」(傍線部ウ)とあるが、どういうことか、説明せよ。(60字程度)
内容説明問題。「それは/そういうこと/ではない(否定)→Aである(肯定)」。⑭段傍線の前部より、「それ」は「周囲を不快にする病猫の面倒をみること」、「そういうこと」は「ボランティア精神/無償の愛(⑮)」となる。Aについては、⑮段落「生き物はエゴイズムに支えられる」とその例としての逸話である⑯段落を挟んで、⑰段落「私が病気の猫を飼い続けたのは/…慈悲心があるからではなく/その猫の存在によって…慈悲の気持ちが引き出されたからである」の最後の部分と対応する。よって「…猫の面倒をみるのは/自発的な無償の愛からではなく/その存在によって引き出された慈悲の気持ちからだ/(と気づき始めた)」となる。
ただ、これだけでは「生き物はエゴイズムに支えられる(⑮)/冥利(⑯)」が活かされていない。そこで後半の部分に、「(猫の面倒をみるのは)その存在によって引き出された慈悲の気持ちと、それに伴う冥利(満足感)からだ」と付け足せばよい。病猫にもたらされた慈悲の気持ちで、それを慈しむことで、自らも満たされた気持ちになるのである(←輻輳した契約(⑰))。
<GV解答例>
周囲を不快にする病猫の面倒をみるのは自発的な愛からではなく、その存在が慈悲心とそれに伴う自足をもたらしたからだと気づいたいうこと。(65)
<参考 S台解答例>
痩せ猫の世話をしたのは、能動的な無償の愛からではなく、病気の猫に自分の中から慈悲の心が引き出されたからだということ。(58)
<参考 K塾解答例>
自分が病猫を助けたのは、慈悲心があったからではなく、猫の儚げな様子によって慈悲を与えて喜ぶ気持ちが喚起されたからだと、気づき始めたということ。(71)
<参考 T進解答例>
筆者が病気の猫を飼い続けたのは、他者に感心されるような主体的に持つ慈悲心からではなく、猫に内なる慈悲心を喚起されてのことだと、徐々に思い始めたということ。(77w)
問四「不意にその臭いのことが愛しく思い出されるから不思議なものである」(傍線部エ)とあるが、どういうことか、説明せよ。(60字程度)
内容説明問題。「その臭い」とは、直前にある「誰もが不快に思う病猫の臭気」である。この一般的には不快な臭いが、猫が死んだ後も愛しく、ふと思い出されるから、不思議だというのである。これ以上、説明する必要がないように思える。しかし、ちょっと待てよ。いくら何でも「肉の腐りかけたような臭気」だけを、愛しく思い出すのは、それは鼻がおかしいだけではなかろうか。ここでの「臭い」が愛しく思い出されるのは、それが猫の記憶とともにあるからと考えるのが妥当だろう。
特に、⑰段落「誰が見ても汚く臭い生き物が、他のどの生き物よりも可愛いと思いはじめるのは、その二者の関係の中にそういった輻輳した契約が結ばれるから」に着目したい。つまり筆者は、慈悲を与え合う輻輳した「契約」(←問三)により、不快な臭気を放つ病猫に無二の愛しさを感じるようになった。ならば、その臭気とともに筆者に愛しく蘇るのは、生前の猫との輻輳した無二の関係性である。その臭気があまりにも強烈に病猫を印象づけたからこそ、その臭いを徴として、猫とのことが思い出されるのである。
<GV解答例>
誰もが不快に思った病猫の臭気がその死後も不思議と強く印象に残り、自己との輻輳した無二の関係を慈しみ蘇らせるよすがになるということ。(65)
<参考 S台解答例>
病む猫の不快な臭いをいとおしむ自分に、生き物のエゴを含む複雑な関係性が呼び起こした意外な愛の現前を覚えたということ。(58)
<参考 K塾解答例>
猫への気持ちは、汚く臭い猫だからこそむしろ愛着を強め、死後もなお、そうした臭いを慕わしく思い出してしまうほど、不可解なものだということ。(68)
<参考 T進解答例>
筆者は世話をし、猫は病という犠牲を払って慈悲心を与えるという、契約関係をもとに猫に愛着を抱いた筆者には、不快な臭気でもその猫の臭いゆえに愛惜されるということ。(79w)