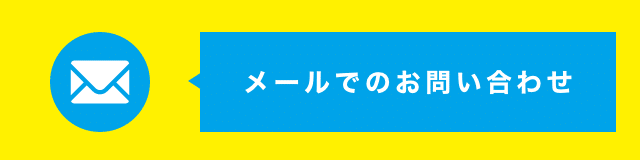目次
- 〈本文理解〉
- 〈設問解説〉
設問(一)「第一人称の死、つねに未来形でしかありえないもの」(傍線部ア)とあるが、どういうことか、説明せよ。(60字程度) - 設問(二)「陳腐だった第三人称の死」(傍線部イ)とあるが、なぜ「陳腐」なのか、理由を説明せよ。(60字程度)
- 設問(三)「この逆説性」(傍線部ウ)とあるが、どういうことか、説明せよ。(60字程度)
- 設問(四)「『われわれ』が『私』を造りあげていた」(傍線部エ)とあるが、どういうことか、説明せよ。(60字程度)
- 設問(五)「それゆえにこそ、第一人称が迎えんとする死こそ、人間にとって極限の孤絶性、仮借なき絶望の孤在を照射する唯一のものなのかもしれない」(傍線部オ)とあるが、なぜそう言えるのか。(100字以上120字以内)
- 設問(六)
〈本文理解〉
出典は村上陽一郎『生と死への眼差し』。本文の形式面に着目しながら、できるだけ本文の言葉だけを手がかりに、内容面の理解を試みる。
①~④段落。第一人称の死は、けっして体験されたことのない、未知の何ものかである。論理的に知りえない死に対して恐怖はどんな形を取るのか。いわゆる死への恐怖は、苦しむ生への恐怖を含むにせよ、それだけではあるまい。生への盲目的な執着が、ヒトが生物であることの明証であるとすれば、死への恐怖はヒトが人間であることの明証であると言えぬだろうか。
⑤~⑧段落。これを消極的な面から考えてみる。第三人称の死は、私にとって、消滅であり消失である。それは、自分の前に立ちはだかる未知の死の何たるかを知ろうとする虚しい努力のための、何らの糧にもならない。(万年筆やハンカチの消失のように)。そして「第一人称の死、常に未来形でしかありえないもの」(傍線部ア)が、現実化したとき、「私」は、完全な孤絶のなかで、それを体験することになる。
このとき、それまで「陳腐だった三人称の死」(傍線部イ)の一つずつが、死の先達として意味をもつように思われかもしれないにせよ、それは空疎な期待に過ぎない。この「私」の死の徹底的孤絶さのゆえに、人は迎えるべき死の恐怖を増幅された形で感ずる。日常的世界の中で常に、人どおしの間の関係性の中で生きてきたわれわれは、たとえ絶海の孤島に独りあってさえ人間的生活の回復への期待を捨てることのないわれわれは、死においてかかる関係性を失って、ただ一人で死を引き受けなければならない。このことへの恐怖こそ、人が人間として生きてきたことの明証となる。あえて「消極的」と呼んだのは「この逆説性」(傍線部ウ)のゆえである。
⑨~⑭段落。他方、このような死への恐怖は、積極的な意味でも、人の人間たることの明証たりうる。それには第二人称が介在することになる。
死において自覚される人の究極的孤絶性を、知性において理解するのは、デカルト以来の西欧近代思想の洗礼を受けたものにとって、むしろたやすい。しかし、知性において理解された表層的孤絶性は、ある立場からすると誤っている。(まず)「私」は外界から隔絶していると思われるが、私の身体さえ拡大されて感じることもある。(ドライヴァの例)。他方、人間は自己により身体を支配・制御していると錯覚しているが、実は、自らの身体的支配は他者の模倣によって獲得される。(蹴上がりの例)。このとき「『われわれ』が『私』を造りあげていた」(傍線部エ)という言い方が許されるだろう。
このような状況は幼児においてもっとはっきりしている。(母親は「僕そんなことだめじゃない」などと言う。このとき、母親と「僕」とは、まだ分離しない「われわれ」意識でつながっている)。幼児は次第にそうした前個我的状況から、母親からの反射の光によって「僕」を僕として捉え、それと反射して母親を第二人称的他者として捉えるようになる。前個我的「われわれ」状況は第一人称と第二人称の他者に分極するのだ。つまり、主体の集合体としての「われわれ」は、前個我的「われわれ」状況のある変型(ヴァージョン)として考えるべきではないか。
⑮段落。この観点から見るとき、個我の孤絶性は、生にある限り、むしろ抽象的構成に近いというべきである。「それゆえにこそ、第一人称が迎えんとする死こそ、人間にとって極限の孤絶性、仮借なき絶望の弧在を照射する唯一のものなのかもしれない」(傍線部オ)。
〈設問解説〉設問(一)「第一人称の死、つねに未来形でしかありえないもの」(傍線部ア)とあるが、どういうことか、説明せよ。(60字程度)
内容説明問題。傍線部は⑥段落にあるが、本文冒頭の「第一人称の死は、決して体験されたことのない、未知の何かである」を承けることを見出だすのは容易。これに⑤段落の内容「(第三人称の死は)自分の前に立ちはだかる未知の深淵としての死の何たるかを知ろうとする、空虚(むな)しい努力のための、何らの糧にもならない」も、「未来形」を徹底するものであるから加えておきたい。
<GV解答例>
私の死は、その死が訪れる時まで、自ら体験されないだけでなく、他者の死からも何一つ参照できない完全に未知のものとしてあるということ。(65字)
<参考 S台解答例>
自己の死は生きている限りけっして体験できるものではなく、生の向こうに想像されるものでしかないということ。(52字)
設問(二)「陳腐だった第三人称の死」(傍線部イ)とあるが、なぜ「陳腐」なのか、理由を説明せよ。(60字程度)
理由説明問題。「第三人称の死=一般的な他者の死S」が「陳腐=ありきたりG」であることの理由を説明する。これも、傍線部は⑦段落だが、⑤段落「第三人称の死は、私にとって、消滅であり、消失であった」を利用する。どういう意味で「消滅、消失」かというと、問一で使った「自分の前に立ちはだかる…」を再び利用して「私の死について何らの示唆を与えない」という意味からである。
ここから「第三人称の死が/私の死について何も示唆しない/消滅であるR1」ことの根本理由に遡及する。これは、⑥段落より「死の体験は/お互いに/完全に孤絶しているR2」という内容を抽出し、「R2ので/R1として/繰り返されるだけだから(→G)」とまとめる。
<GV解答例>
他者の死は、死の体験において完全に孤絶している自他の関係の中で、個的な死については何も示唆しない消滅として繰り返されるだけだから。(65字)
<参考 S台解答例>
他者の死は事物の消滅、消失と同様に、未知な自己の死については何も教えてくれるものではないと思えるから。(51字)
設問(三)「この逆説性」(傍線部ウ)とあるが、どういうことか、説明せよ。(60字程度)
内容説明問題。傍線部は⑧段落の締めの部分にあり、「この」という指示語で前内容を承けるわけだから、⑧段落の内容を過不足なく繰り込むようにする。「逆説」は「一見矛盾するが/実は真である内容」。まずは「矛盾」する対を指摘すると「人は孤絶の中で死ぬ(X)//人は関係性の中で生きる(Y)」となる。そして「Xに恐怖を感じることが/かえってYを示す」のである。
これに加えて「絶海の孤島に独りあってさえ…人間的生活への微かな期待を決して捨てることのないわれわれ」という内容を吟味する。「AさえB」という表現は「特に顕著な事例(A)もBに含まれることを提示する」ものだから、「絶海の孤島に独りあった者でさえ(関係性を生きている)」を繰り込むことで、こうした逆説は人間全般に当てはまることが指摘でき、有意であるといえる。
<GV解答例>
他者と共有できない個的な死への過剰な恐怖が逆に、孤立した生にあった者さえ、人が他者との関係性に規定されてきたことを示すということ。(65字)
<参考 S台解答例>
自己の死という完全な孤絶への恐怖を抱くことが、人間が関係性の中に生きたことをかえって明らかにするということ。(54字)
設問(四)「『われわれ』が『私』を造りあげていた」(傍線部エ)とあるが、どういうことか、説明せよ。(60字程度)
内容説明問題。『われわれ』(A)と『私』(B)に加え「A→B」の関係性を説明する。傍線部は「このとき」と前文までの「蹴上がり」の具体例を承けるが、次⑬段落冒頭「このような状況は、幼児においてもっとはっきりしている」とあり、⑬段落締め「主体の集合体としての『われわれ』(←蹴上がり)は、前個我的『われわれ』状況(←幼児の状況)のある変型として考えるべきではないか」とあるので、⑬段落の「幼児の事例」を参照するのが一般妥当であろう。
そこで「幼児は…前個我的な状況から、反射の光によって、「僕」を僕として捉えるようになり、それと反射的に母親を第二人称的他者として捉える(=第一人称と第二人称の他者の分極化)」を参照する。つまり「自他が融合した『われわれ』状況での/行為の交換により/他者と分離した『私』が現れる」(A→B)ということだろう。これは「蹴上がり」にも当てはまる。
あとはAとBの言い換えだが、Aについては「前個我的『われわれ』状況」をさらに「個分立以前の自他混融状況」と自力で言い換えたが、無理せず「前個我的『われわれ』状況」でもよい。Bについては⑫段落「人間は自己によって自らの身体を支配・制御しているかのように錯覚」を利用した。⑩段落に出てくるデカルトの、いわゆる「心身二元論」における人間観である。筆者に従えば『われわれ』こそ「本質」であり『私』は「現象(=本質の発現)」にすぎないのである。
<GV解答例>
個分立以前の自他混融状況における相互行為の反射を通して、近しい関係にある他者と分離された、身体を統御する自己が現象するということ。(65字)
<参考 S台解答例>
人は知性により人間の孤絶性を理解したつもりでいるが、実は他者との身体性を伴った関わりの中にあるのだということ。(55字)
設問(五)「それゆえにこそ、第一人称が迎えんとする死こそ、人間にとって極限の孤絶性、仮借なき絶望の孤在を照射する唯一のものなのかもしれない」(傍線部オ)とあるが、なぜそう言えるのか。(100字以上120字以内)
理由説明型要約問題。基本的な手順は
1⃣´ 傍線部自体の端的な理由を示す。(解答の足場)
2⃣「足場」につながる論旨を取捨し、構文を決定する。(アウトライン)
3⃣ 必要な要素を全文からピックし、アウトラインを具体化する。(ディテール)
1️⃣´ 傍線部をザックリ捉え「死こそ人間にとって極限の孤絶性を照射する唯一のものG」の理由を端的に述べる。傍線部が「それゆえにこそ」で始まるので前文が理由の核となる。「個我の孤絶性は/少なくとも生にある限り/抽象的構成に近い」とあるが「抽象的構成に近い」を「現実に即していない」と捉え返す。それでは現実は、と自問することで「人は生にある限り/他者との関係性にあったからR1(→G)」という答えの核が見えるであろう。
2️⃣ 傍線部のある最終段落は、段落末文である傍線部と、1️⃣で考察した理由の核(R1)となる傍線部前文の2文からなる。この文(R1)が「この観点から見るときに」と、これまでの全文内容を踏まえて続くことから、R1(傍線部の直接理由)の理由となる根本理由R2を全文を踏まえて指摘する。当然、設問三(消極面A)と設問四(積極面B)で考察した内容が、全文構成の上でR2の二側面、つまり「人が常に他者との関係性を生きているR1」の二つの理由といえる。以上より、解答の基本構文は、設問三と設問四の考察を踏まえて、
「そもそも人は生存の始めから前個我的「われわれ」状況にありB/他者と共有できない個的な死への過剰な恐怖からもA/人は死に到るその時まで/他者との関係性を生きているといえるから」となる。
3️⃣ 上の段階でほぼ答えとしてよいが、傍線部の前文「個我の孤絶性は/生にある限り/抽象的構成である(=現実に即していない)」にも改めて触れておこう。もちろんこれは、⑩⑫段落にあるデカルト以来の近代的な人間観(自己は身体を制御する完結した存在)と対応する。こうした想定が誤りだと指摘することも、傍線部の筆者の結論を補強することになり、有意であるといえる。
<GV解答例>
近代においては他者と明確に区別された統一的な自己を想定するが、そもそも生存の始めから人は前個我的「われわれ」状況にあり、他者と共有できない個的な死への過剰な恐怖からも、人は死に到るその時まで、常に他者との関係性の中で生きているといえるから。(120字)
<参考 S台解答例>
第三者の死は単なる消滅、消失でしかなく、けっして体験することのできない自己の死においてのみ、人は他者との身体性を伴った関係性の中に生きていることを確認し、抽象的な孤絶を超えて、そこから引き裂かれる究極的な孤絶への恐怖を覚えさせられるから。(119字)
設問(六)
a. 空疎 b. 錯覚 c. 模倣 d. 抱擁