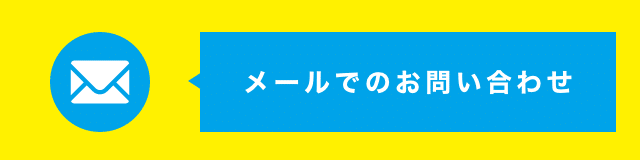目次
〈本文理解〉
出典は松浦寿輝『青天有月』(随想)。
①段落。P・G・K・カーンとS・M・ポンピアは一九七八年に発表した論文の中で、現存種のオウムガイの殻の表面に見える成長線を数え、隔壁の間に挟まれた小室の一つ一つに平均三十本の細線が含まれること、その数はどの殻を見てもまた同じ殻のどの小室を見てもほとんど変わらないことを報告している。深海に住むオウムガイは夜になると海面に浮かび上がってくる。太陽の周期に合わせて浮沈するオウムガイの細線は、一日ごとの成長の記録だと考えられるだろう。隔壁は月の周期に同調して作られるのだと仮定すれば、毎月三十本ということで数はぴったりと合うわけだ。カーンとポンピアは四億二千万年前から二千五百万年前にわたるオウムガイ類の化石について調査を行った結果、一小室あたりの細線数が、現存で三十本、新しい化石で約二十五本、最古の化石で九本と、年代の古いものほど規則的に少なくなることを明らかにした。すなわち、四億二千万年前の地球では、ひと月はたった九日間しか持っていなかったのである。これは当然のことであり、その理由を説明するのは簡単だ。天文学と地球物理学が明らかにしているように、地球は潮汐摩擦により減速し角運動量を失うが、月はその分の運動量を受け取り地球からの距離を大きくしながら公転するからである。月は少しずつ地球から遠ざかりつつある。地球の自転が一日二十一時間しかなかった四億二千万年前に、月は今よりずっと近いところにあり、わずか九太陽日で地球の周囲を公転していたのだ。古生代のオウムガイはすでに原始的な眼球を備えていた。彼らはその眼で、夜ごと深海から浮かび上がってきては、今われわれが見ている月とは比べものにならないほど巨大な月を眺めていたのである。
②段落。オウムガイの殻に残った細線の数が意味するものに関してグールドはカーンとポンピアの仮説にいくぶんかの懸念を呈しており、それはまことにもっともな点を衝いているのだが、九本が正確に九日間と対応していると断言するのは行き過ぎであるにせよ、少なくとも「彼らの推論の大まかな方向づけ」(傍線部(A))はそのまま諾ってよいもののように思われる。いや正直に言えば、太古の海で巨大な月を見つめているオウムガイに思いを致すのはあまりにも魅力的なので、グールドの懐疑論には「耳を貸したくないという気持が強いのだ」(傍線部(B))。
③段落。…四億二千万年前の月は、中天まで昇ってきてもなお巨大な姿で四囲を圧し、その堂々たる輝きで満天に鏤められた星々の煌めきもかすんでしまうほどだったことだろう。昔の光とは、今の光とはまったく違うもののことである。それは、今の光から類推によってイメージを作ることができるようなものではないはずだ。わたしは今、それを想像してみようとは思わない。…四億二千万年前の月光はわたし自身の肉体の延長をはるかに越えた昔の光であり、わたしはそれを一度も見たことがないしこれから見られようはずはない。もちろん何とかそれを想像してみよう、脳裡に思い描いてみようと試みることはできる。前世紀のフランス詩人コント・ド・リールにとって文学創造とはそうしたことだった。だが想像力が豊富であると貧弱であるとを問わず、「想像するとはそれ自体、精神の営為として基本的に貧しいものでしかありえない営みだと思う」(傍線部(C))。詩人の富として語られる想像力の徳について、わたしはかなり懐疑的である。絵空事としか見えぬ弱々しい想像もあろうし迫真の力強さを帯びた想像もあるだろうが、いずれにせよ想像されたものは、結局想像されたものでしかないからである。いかなる場合でも想像は現実に及びようがない。
④段落。四億二千万年前の月はたしかに地球の海を照らし出していた。オウムガイたちは波間に揺られながらその光を見つめていた。これは、今われわれが想像力を行使して構成しようと努めるイメージとは無関係に存在している、確固とした事実である。昔の光は、昔、たしかにあった。この「あった」の重さにはいかなる想像力も追いつきようがない。この光を古生代のオウムガイが見つめていたという過去の現実は、化石の殻の小室に刻まれた九本の成長線がはっきり証し立てている。中天を圧して輝きわたっている巨大な月を、オウムガイたちはたしかに見つめていた。わたしたちはそれを見ることができないが、このオウムガイたちはそれをたしかに見ていたのであり、のみならず自分がその光を見ていたという事実を自分自身の軀に刻印し、四億二千万年後の今日に残しているのである。彼らがみずからの肉体に残った痕跡の形でいわばわれわれに遺贈してくれたこの証言を通じて、われわれはそうした光が存在したことを知ることができる。「わたしが感動するのはここのところだ」(傍線部(D))。それを見ることができないが、かつて在りし日にそれを見ていた者を見ることができる、── 彼がたしかにそれを見ていたという現実を証明する物質的な証拠を見ることができ、つまりはそれによってその光を知ることができるということ。四億二千万年前の波間にそうした月光がそそいでいたことを、今わたしは知っているということ。知ることとは、ここで、想像することをはるかに越えて豊かで本質的な営みとしてあるというべきである。見ようとしても見られないものを想像するというのはしばしば安っぽい文学的感傷でしかない。だが、いかなる想像も追いつきようのないものを知ることができるというのは、これまた何と人を興奮させる出来事であることか。
〈設問解説〉問一 (漢字)
(ア) 懸念 (イ) 四囲 (ウ) 絵空事 (エ) 迫真 (オ) 行使
問二 「彼らの推論の大まかな方向づけ」(傍線部(A))の内容を説明せよ。(五行:一行25字程度)
内容説明問題。「彼らの推論」とは、カーンとポンピアの仮説であり、①段落でまるまる説明されている。その「大まかな方向づけ」について、筆者は「そのまま諾なってよい」、むしろ肯定したいという気持ちを持っている(→問三)。ここで、①段落を漠然とまとめてはならない。筆者が肯定したいと思う「方向づけ」の「末」にくるものを捉え、それにつながるように①段落の内容を(再)構成する(本文の叙述の順とは限らない)。ふつう推論の方向は、より蓋然性の高いものから低いものへと移るはずである。
そこで方向づけの「末」だが、傍線の直前に「九本が正確に九日間に対応していると断言するのは行き過ぎであるにせよ」とあるように、かつての月の公転日数とオウムガイの殻の小室に刻まれた細線(成長線)の対応が推論の中心にあるようである。実際、結論部にあたる最終④段落でも「彼らがみずからの肉体に残った痕跡の形で…われわれに遺贈してくれた…証言/物質的な証拠」を通じて、かつての月の光を「知る」ことができることに筆者は感動するとしている(→問五)。以上より、「末」は「四億二千万年前の月の公転日数とほぼ対応するように/オウムガイが成長線を自らの殻の小室に刻んでいたのではないか」(P)ということになる。
ここから①段落に戻って細かく検討すると、Pの推論は段落半ばにあり、後半に「(四億二千万年前)月は今よりずっと地球に近いところにあり、わずか九太陽日で地球の周囲を公転していた」(Q)とある。「九日/九本」という数字は置くとして、Qについては「すでに天文学と地球物理学が明らかにしている」とあり、Pよりも蓋然性が高いので、Pを導く条件の一つと考えられる。この「Q→P」という推論の方向を軸に、Pを導くのに必要な条件として「(オウムガイは)太陽の周期に合わせて/夜になると海面に浮かび上がってくる」「古生代のオウムガイはすでに原始的な眼球を備えていた」の2つの要素を繰りこみ、解答を構成する。
<GV解答例>
四億二千万年前の月は現在よりずっと地球の近くにあり、太陽の周期に合わせて夜になると深海から浮上してくるオウムガイは、その原始的な眼球で巨大な月を捉え、当時の月の短い公転日数とほぼ対応するように成長線を自らの殻の小室に刻んでいたのではないかということ。(125)
<参考 S台解答例>
オウムガイの殻の細線が太陽の周期と、隔壁が月の周期と同調する場合、隔壁間の細線数はひと月の日数を示し、太古のオウムガイの隔壁間の細線数が現在より少ないことから、当時、ひと月は現在より短く、月は現在より地球に近い位置を公転していたと推定すること。(122)
<参考 K塾解答例>
オウムガイの化石に刻まれた成長周期に基づき、地球と月の距離の変化を算出すると、四億二千万年前に生息していたオウムガイは、夜ごと深海から浮上し、現在よりもはるかに地球に近く巨大な月が、圧倒的な輝きで夜空を照らす光を、眺めていたにちがいないということ。(124)
問三 「耳を貸したくないという気持が強いのだ」(傍線部(B))には、筆者のどのような心情が込められているか、わかりやすく説明せよ。(四行:一行25字程度)
表現意図説明問題。このタイプの問題は、本文の主題についての内容レベルで答えるのではなく、なぜそうした記述(表現Mとする)をしているのかという「メタレベル」で答えなければならない。具体的には「表現M」の前提となる記述を確認し、その上で「表現M」を承けた後にどう記述が展開されるかを追う(ここに「表現意図」が顕在化するはずだ)。
まずは前提の確認から。①段落でまとめられたカーンとポンピアの仮説(問二)に対し、筆者が本文で依拠する科学史家(←注)のグールドは、「いくぶんかの懸念」(以下②段落)を呈する。これに筆者も「もっともだ」とした上で、しかし彼らの推論の大まかな方向づけについてはそのまま「諾ってよい」とし、さらに(というより)「正直に言えば/太古の海で巨大な月を眺めているオウムガイに思いを致すのはあまりに魅力的なので」、グールドの懐疑論には「耳を貸したくないという気持が強いのだ」(傍線部(B))とするのである。つまり、筆者もカーンらの仮説に対する「科学史家」グールドの懐疑論には、基本的には同意している。カーンらの仮説(九本の細線と九日の公転日数が正確に対応する)は、たしかに科学的な厳密性を欠く。かといって、それで「仮説」を排してしまうのは「巨大な月を眺めるオウムガイに思いを致す魅力」からして、あまりにもったいない、という気持ちなのである。
これで傍線の含まれる心情は、ずいぶん具体化できた。しかしこれでは不十分で、先述した通り「表現意図」は「表現M」の後の展開を見ないと確定できないのだ。それで③段落では、カーンらの仮説からキープされる「太古に存在した巨大な月」を話題に、想像は現実に及ばないことが述べられる(→問四)。それを承けて最終④段落では、「オウムガイが巨大な月の短い公転速度に対応して成長線を刻んだ」(P)という「事実」を「知る」ことができることに、筆者は感動を覚えると結ぶのである(→問五)。そのPを「事実」とするためには、カーンらの仮説を、それが科学的な厳密性を欠くとも、一旦飲み込まないといけないというわけである。
以上の考察より、内容自体の説明は最小限にして傍線の「表現意図」(メタ)を説明すると、「カーンらの仮説へのグールドの懐疑論はもっともだ→しかし科学的な厳密性をつきつめて排するにはあまりに魅力的な含みがある→よって仮説から引き出される可能性をあえて保っておきたい(という心情)」となる。画竜点睛となった。
<GV解答例>
カーンとポンピアの仮説に対するグールドの懐疑論はもっともなことだが、科学的な厳密性をつきつめて排するにはあまりに魅力的な含みがあるので、その仮説から引き出される可能性をあえて保っておきたいという心情。(100)
<参考 S台解答例>
カーンとポンピアの仮説に対するグールドの懐疑論に科学的妥当性を認めつつも、懐疑論を拒み、仮説を大筋で認めて、太古の海で巨大な月を見つめているオオムガイへ思いを致す魅力を優先したいという心情。(95)
<参考 K塾解答例>
オウムガイの隔壁間の数がひと月の日数と一致するという仮説への疑念にも一理あると思いつつ、科学的な正確さよりも、オウムガイが太古の海に漂いながら巨大な月を眺めているという情景に魅きつけられる心情。(97)
問四 「想像するとはそれ自体、精神の営為として基本的に貧しいものでしかありえない営みだと思う」(傍線部(C))について、筆者はなぜこのように思うのか、説明せよ。(三行:一行25字程度)
理由説明問題。「想像力が豊富であると貧弱であるとを問わず/想像するとは/精神の営為として/貧しい」理由を考える。「精神の営為として」(Z)とあるから、「想像する」(X)の他にZに含まれるYがあって、それとの比較でXは「貧しい」となるはずである。
手がかりになるのは、傍線の次④段落「この(巨大な月が)「あった」の重さにはいかなる想像力も追いつきようがない」という記述。以下、その「過去の事実」を「化石に刻まれた九本の成長線がはっきり証し立ててい」て、その「物質的な証拠」をわれわれは「見る」ことができ、そうした月の光が存在したことを「知る」(←「想像することを越えて/本質的な営み」)ことができる、と続く。ここで「想像する」(X)と比較されるYは「見る/知る」になるだろう。その「見る/知る」(Y)に対応するのが「あった」という「事実(現実)」ならば、「想像する」(X)は「見る」という経験や実像に即していない漠然としたものである(③段落)。したがって、それがいくら「迫真の力強さを帯びた」(③)ものであっても、「確固とした事実」(④)に根づいたYには及びようもない。よって「精神の営為として/基本的に貧しい」(G)といえるのである。
<GV解答例>
経験される実像を持たずに漠然と広がる想像力が、たとえ迫真の像を結ぶものであったとしても、確たる現実に直面して知覚する働きの重みには及びようもないから。(75)
<参考 S台解答例>
想像は想像にとどまり、いかなる場合でも、想像力による人工的なイメージと無関係に存在している確固とした事実である現実の重さに及びようがないから。(71)
<参考 K塾解答例>
どれほど豊かでも、存在しないものを思い描く想像は、確固とした事実が示す存在の重みには及ばず、知るという精神の本質的な営みに比べれば感傷にすぎないから。(75)
問五 「わたしが感動するのはここのところだ」(傍線部(D))はどういうことか、説明せよ。(四行:一行25字程度)
内容説明問題(主旨)。「「ここ」に、筆者は感動する」と前後を入れ替えて、「ここ」の指す内容を具体化したらよい。当然「ここ」は、前文「彼ら(オウムガイ)がみずからの肉体に残った痕跡の形で…遺贈してくれた証言…を通じて…そうした光が存在したことを知ることができる」を承ける。また、傍線の次文「それを見ることはできないが…彼がたしかにそれを見ていたという現実を証明する物質的な証拠を見ることができ…その光を知ることができるということ」、次々文「四億二千万年前の波間にそうした月光がそそいでいたことを、今わたしは知っているということ」の2文も、「(それは)~ということ」の形で傍線の「ここ」を承けていることは明らか。さらに、同④段落最終文(本文末文)「いかなる想像力も追いつきようがないものを知ることができるというのは/…何と人を興奮させる出来事であることか」も、傍線「…感動するのは/ここのところだ」を前後入れ替えた形で内容的に対応している。この前後4文を踏まえて、「ここ」を具体化する。
大切なのは、具体的になり過ぎて筆者の感動するツボがぼやけたものにならないようにすることである。骨格は「見ることができない/想像するのも虚しい→しかし物質的な証拠を通じて時を越えた事実を知ることができる→そのことに筆者は興奮を覚える」となる。この骨格をキープした上で、「太古の巨大なな月→オウムガイに刻まれた細線→その月(光)が存在した事実」という具体的文脈を加える。あまり一般化し過ぎても筆者の感動のツボを外すように思われる。やはり、太古の巨大な月、それをオウムガイが自らの身に刻み今に伝えるという具象性を伴うからこそ、筆者は(そしてそれをたどる読者も)そこに果てのないロマンを感じずにはいられないのではないだろうか。
<GV解答例>
太古に地球を照らした巨大な月は見ることができず想像するのも虚しいが、オウムガイに刻まれた細線が物質的な証拠となり、その月が存在したという事実を今に知ることができることに、筆者は興奮を覚えるということ。(100)
<参考 S台解答例>
現実を実体験したものに残る物質的な証拠を通じて、現実を実体験しえない人間がいかなる想像も及ばない現実を知ることに、筆者は、想像を越えて豊かで本質的な営みを認め、興奮を覚え、心を動かされるということ。(99)
<参考 K塾解答例>
太古のオウムガイが巨大な月を眺めていたという事実が殻に刻印されており、そうした物的証拠により、四億二千万年後の人が、太古の月光とそれを眺める生物という、想像を越えた事実を知り、胸がふるえるということ。(100)