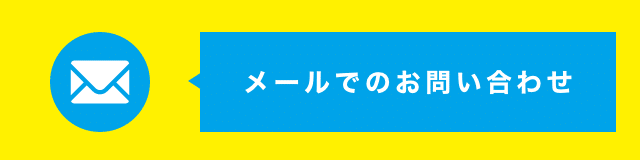〈本文理解〉
出典は檜垣立哉『食べることの哲学』。
①②段落。食べものというのは、ほとんどが「生きたもの」である。このいい方はいささかオブラートにくるんだものであり、われわれは何かを殺して食べているのである。ヴェジタリアンの場合でも、食べてよいとされる植物もまた生物であることに変わりがない。何をどういおうと、われわれは生き物を食べ、そのかぎりでそれを殺している。とはいえ、とりわけ近代社会においてはみだりに生き物を殺すことを推奨する文化はほぼ存在しない。一方では生きているものを殺してはダメだというのは文化の基本的な原則でもある。だが、同時にわれわれは自分が日々自分が生きるなかで、大量の動物や植物を、やはり殺して食べているのである。現代文明においてはまさに、みえないところでそうした殺戮がおこなわれる。これは端的に矛盾ではないか。
③段落。すがすがしいまでに「この矛盾」(傍線部A)を問い詰めるのは宮沢賢治である。…人間は生き物を食べないと自分が死ぬ。しかし、自己の倫理に忠実であれば、そもそも自分が死ねばよいのではないか。宮沢の問いそのものはここまで達してしまう。これは極限的な「食べない」に通じるものである。
④段落。そしてまたこの場合、「ここまでなら食べてよし」「これは食べていけない」という問いにむすびつくことも往々にしてある。これもまた「文化相対主義が幅をきかせる」(傍線部B)議論のようにみえる。曰く、日本人は魚を生で食べるが、以前はそのようなことは世界のどこでも気持ち悪がられた。ムスリムはハラルフードしか食べない。インドでは牛は聖なる生き物なので食べない、等々。だが、こうした議論のそれぞれは、実際にはさして重要ではない。この議論には、あるゼロ点ともいうべき根底がある。それは「人間は人間を食べない」ということである。これはカニバリズムのタブーといわれる。そして、人間が人間を食べるということは、さまざまな人類学のなかの(西洋中心的な)「野蛮人」の表象のなかにみうけられることになる。…
⑤⑥段落。このことは食育にも連関する。大阪の豊能町でおこなわれた、殺して食べることを前提に豚を飼うという、実験的ないのちの授業の顛末をまとめた『豚のPちゃんと32人の小学生』という本がある。この試みは、哲学的にみれば、文化と動物との人間としての臨界を、教育という視点からあつかうことにより、それが無理であることを露呈させてしまう貴重な実験であるようにみえる。率直にいえば、これは教育としてはとても褒められたものではない。…食育や、食べるということをいかに道徳的にあつかったところで、そこには「生き物は生き物を食べる」という絶対的な仕組みが介入し、それについて教育は、ほぼ何もいえないということが明らかにされるのである。さて、ではどうすればよいのか。これこそが食にかんする哲学の大テーマではないのか。
⑦⑧段落。食にかかわる矛盾にまつわる問題系は、もちろん文化間での「食べてよいもの」「よくないもの」の対立にも展開できる。(太地町のイルカ漁を批判する反捕鯨運動の例)。こうした運動をどう考えるのか。人間同士の利害がおそらくいちばん対立する位相は「こういう場面」(傍線部C)であるだろう。人間と食をめぐる事態は、確かにさまざまな禁止とそのせめぎあいのなかにある。ただしそれは単純な文化間差異の問題なのではない。むしろより複雑な人間と自然とのあいだに横たわる何かに触れるものではないか。
⑨⑩段落。ここまでのはなしだとだいぶ陰鬱な印象をうけるかもしれないが、一面こうしたタブーや暗さのうえに人間の味覚がある。それは残酷さをひきうけたかぎりでの、ある種の味覚の洗練なのかもしれない。この点については、レヴィ=ストロースの料理の三角形から「人間にとって何が旨いのか」という問いをたててみたい。レヴィ=ストロースは、もともとは神話をあつかう人類学者であるが、料理に触れるときには神話と料理の相同性についてとりあげている。神話は、理解しがたい自然の事象に対し、それと人間の世界とを調停する手段であるとレヴィ=ストロースはいう。神話には明確な論理があり、自然の事象を文化の事象で説明するためのひとつの調停であるとされるのである。そしてそれは料理についても同じだという。
⑪⑫段落。食べるものは自然物である。料理とはこの自然物に何らかの人工的な加工をほどこすことにほかならない。この加工の様式には、「生のもの」「火にかけたもの」「腐敗させたもの」によって形成される「料理の三角形」として提示されるが、ここでは「腐敗させたもの」という特殊な領域をとりわけ強調したい。腐敗させることとは、一見すると食を食でなくさせる行為であるかのようにみえるがそれは違う。腐敗は発酵とむすびつき、実に絶妙な人間の味覚そのものを可能にするのである。発酵がなければ、味わい深い料理は存在しない。そして発酵というのは人間が手を加えるというよりも、その期間それを自然のなかに放置することによって旨みをひき出すという「自然と文化の接合点を示す現象」(傍線部D)である。納豆や味噌や醤油、干物や保存食、そしてもちろんアルコール、これは人間の食の原点である。これを哲学的な主題として押さえることは、きわめて重要な意味をもつに違いない。
〈設問解説〉問一 (漢字)
1推奨 2端的 3往々 4忌避 5啓発 6荒唐 7露骨
問二 「この矛盾」(傍線部A)とはどのような矛盾か。(50字以内)
内容説明問題。「この矛盾」(③段冒頭)の「この」は前②段落末文「これは端的に矛盾ではないか」を承ける。「これ(は…矛盾)」の指す内容は、そこから2文遡った「だが」の前後、「生きているものを殺してはダメだというのは文化の基本的な原則でもある」(X)と「(だが)…われわれは日々自分が生きるなかで、大量の動物や…植物を、やはり殺して食べているのである」(Y)となる。Yの次の文「…みえないところでそうした殺戮がおこなわれる」は、「矛盾」点がボケるので、Yの付加説明と見なして、解答には入れない。対比を明確にして、「文化──生き物を殺すことを否定」(X)、「生存──生き物を殺して食べる」(Y)と配置し、「XしながらYするという矛盾」とまとめる。
<GV解答例>
人間は、文化において生き物を殺すことを否定しながら、生存において生き物を殺して食べているという矛盾。(50)
<参考 S台解答例>
近代社会では生き物を殺すのは文化の基本原則として禁止されているのに、日々生き物を殺し食べている矛盾。(50)
<参考 K塾解答例>
殺生は文化的な禁忌なのに、現代文明でも、人が生きる中で日々暗々裏に大量の生き物を殺し食べていること。(50)
問三 「文化相対主義が幅をきかせる」(傍線部B)とあるが、どのようなことか。(60字以内)
内容説明問題。傍線の前後が「これもまた…(B)…議論」となっているので、「これ」の指す内容「「ここまでなら食べてよし」「これは食べていけない」という問い」(X)を踏まえ、「食べてよい生き物とそうでない生き物の境界を決める議論では(X)/文化相対主義が重用される(B)」と解答構文を決める。
あとは、「文化相対主義」(Y)のここでの文意に沿った説明だが、傍線の次の文が「曰く」で始まり、日本、ムスリム、インドのYの例を挙げる。さらに、次文が「だがこうした議論のそれぞれは、実際にはさして重要ではない」となり、以下新たな論点(ゼロ点としてのカニバリズムのタブー)に移るので、解答に参照できるのは、「曰く」以下の3つの例のみに限られる。といっても「例」はそのまま解答に使えないから、Xからのつながりと「例」との対応を踏まえ、語義(常識的理解)に基づきYを具体化しなければならない。そこで、日本人なら生の魚、ムスリムならハラルフード、インド人なら牛食の禁忌というように、どこまで食べてよいかの議論では、「文化ごとの固有性を尊重すべきという立場」(Y)が重用される、とまとめる。
<GV解答例>
食べてよい生き物とそうでない生き物の境界を決める議論では、文化ごとの固有性を尊重すべきという立場が重用されるということ。(60)
<参考 S台解答例>
何を食べてよいか、食べてはいけないかの文化ごとの違いは、それぞれの基づく規範が異なるからだと説明されてしまうということ。(60)
<参考 K塾解答例>
世界各地に見られる、生き物を殺して食べる多様な事象について、文化的な差異との関連に基づく声高な主張が蔓延するということ。(60)
問四 「こういう場面」(傍線部C)とはどのような場面か。(60字以内)
内容説明問題。「人間同士の利害が…いちばん対立する位相は「こういう場面」(C)」(⑧)の「こういう」承ける内容は、前⑦段に遡り、具体例を挟んだ、⑦段冒頭「文化間での「食べてよいもの」「よくないもの」の対立にも展開できる」。太地町のイルカ漁を批判する反捕鯨運動の例を踏まえて、Cを「同じ生き物について、食べてよいか、否かをめぐる対立が展開する場面」と具体化する。
あとは、⑧段傍線以下の部分、「人間と食をめぐる問題は…単純な文化間差異の問題なのではない…より複雑な人間と自然とのあいだに横たわる何かに触れるものではないか」を踏まえ、「より複雑な人間と自然とのあいだに横たわる何か(X)/に起因するC」と解答を構成する。もちろんXは言い換える必要があるが、本文に直接言い換えている表現は見当たらない。例を踏まえると、そこにある対立は、イルカ(クジラ)を「自然」の恵みと考えるか、哺乳類として「人間」の延長と考えるかの対立と見なせる。これよりXを「人間と自然の関係規定に対する文化ごとの違い」と具体化した。
<GV解答例>
人間と自然の関係規定に対する文化ごとの違いに起因する、同じ生き物について、食べてよいか、否かをめぐる対立が展開する場面。(60)
<参考 S台解答例>
食べてよい生き物とそうではないものを区別する絶対的な規範がないため、そのことに関する文化間の対立が深刻化してしまう場面。(60)
<参考 K塾解答例>
生き物が生き物を食べるという人間と自然との絶対的な関係の中で、食べる生き物をめぐる分化間の差異が顕在化してくる場面。(58)
問五 「自然と文化の接合点を示す現象」(傍線部D)を料理に見いだすのはなぜか。本文全体の論旨を踏まえ100字以内で説明せよ。
理由説明問題(主旨)。傍線部(⑫)は料理の中でも「腐敗/発酵」について述べる文脈に位置づけられるが、設問では「「自然と文化の接合点を示す現象」(D)を料理に見いだすのはなぜか(G)/本文全体の論旨を踏まえ」というように「料理一般」に位置づけ直して答えなければならない。広く見て、⑩段落「神話は、理解しがたい自然の事象に対し、それと人間の世界とを調停する手段である」「料理についても同じだ」(ともにレヴィ=ストロースに依る)と、⑪段冒頭「食べるものは、自然物である/料理とはこの自然物に何らかの人工的的な加工をほどこすことほかならない」を根拠にする。これより、「自然と人間の世界(→文化)の根本的な対立を/自然物に人工的な加工をほどこすことで調停しうるのが調理だから(→G)」と解答の骨格が導ける。
あとは、「本文全体の論旨を踏ま」え、「食べること」における「自然と文化の根本的な対立」とは何かを具体化する。本文では冒頭において(①②)、「食べること」における根本的な矛盾が指摘された。問二で考察した通り、「文化において生き物を殺すことを否定」(X)しながら「生存において生き物を殺して食べる」(Y)ということだった。「食べること」における「自然と文化の根本的な対立」のうち、Xが「文化」に相当するなら、Yが「自然」に相当するはずだが、どういう意味で? Yは人間の身体性に基づく生存欲求で、その意味で「自然=本性」なのである。
以上の考察に加え、前問までの解答で根拠としていない重要な論点、④段後半「ゼロ点(食の下限)としてのカニバリズムのタブー」の要素を「文化」の説明に繰りこむ。それで解答の前半部を、「食において人間は生存のために食べながら/食人の禁忌を基点として殺し食べることを制御する文化を築いたが/この欲求の自然と文化の根本的な対立を…」として仕上げる。
<GV解答例>
食において人間は生存ために食べながら、食人の禁忌を基点として殺し食べることを制御する文化を築いたが、この欲求の自然と文化の根本的な対立を、自然物に人工的な加工をほどこすことで調停しうるのが料理だから。(100)
<参考 S台解答例>
人間が生き物を殺して食べるのは文化を超えた絶対的な自然の摂理であり、その残酷さをひきうけ、自然の中に放置し発酵させた自然の素材から深い味わいを引き出す料理は、自然と文化の新たな関係を開くものだから。(99)
<参考 K塾解答例>
文化的な禁忌に反して、生き物を殺して食べざるを得ない人間にとって、料理は、生き物という自然物に文化的な加工をほどこし、腐敗した自然物をも享受させるものであり、自然と文化の調和を象徴する行為だから。(98)