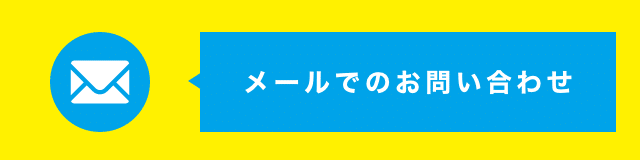目次
〈本文理解〉
要約問題は、形式に則った客観的な読み取りと、そこから得られる内容理解と本文構造に即した表現力を問うものである。その点で、現代文における学力がストレートに試されているといえる。したがって、一橋大学の受験生でなくとも、100字~200字程度の要約をして的確な添削指導を受けることは、学力養成の良い機会となるだろう。
要約作成の基本的手順は、以下の通り。
1️⃣ 本文の表現に着目して重要箇所を抽出する(ミクロ読み)。
2️⃣ 本文をいくつかの意味ブロックに分けて、その論理構成を考察する(マクロ読み)。
3️⃣ 本文の論理構成に基づき、要約文の論理構成の骨格を決める(例えば、本文が2つのパートに分かれていれば、要約文も原則2文で構成するとよい)。
4️⃣ 骨格からもれた付加要素を、構文を崩さない程度に盛り込んで仕上げとする。
出典は山口裕之『「大学改革」という病──学問の自由・財政基盤・競争主義から検証する』。条件なしで200字以内の要約が求められる。
1️⃣ ①段落。ヨーロッパにおいて大学は、教師と学生が自発的に集合して成立した自治的な組織に由来するが、アメリカの場合は、教会や州政府、さらには大富豪によって人為的に設立されたものである(a)。大学の支配権は、教員組織ではなく、教育に携わらない設置者たちの手に握られていた(b)。…科学の進展とともに、自然科学については、自由な研究や教育が認められるようになっていった(c)。
②段落。しかし、社会科学における「学問の自由」は、資金を提供した企業家たちの利害と直接に対立する場合があったので、一九世紀末や二〇世紀初頭になっても、まだ認められるものではなかった(d)。
③段落。ドイツの場合、大学教授は国家の被雇用者であり、一般市民には認められない特権的な自由が認められていたが、アメリカの場合、一般市民が憲法によって「言論の自由」を保証される一方、私企業の被雇用者として大学教授にはそれが認められていないという、皮肉な事態になっていた(e)。
④段落。それゆえ、アメリカにおける「学問の自由」を求める闘争は、自分たちが所属する大学の経営陣に対する闘争という形をとった(f)。(テニュア(終身在職権)の獲得の例~⑤段落)。
⑥段落。アメリカでは、二〇世紀初頭になってようやく「学問の自由」という概念が登場し大学教授たちはその実現を目指すようになった(g)。社会科学におけるその実現には紆余曲折があったが、自然科学の分野では、研究の自由は早々と実現されていった(h)。
⑦段落。(ベン=デービッドによる説明。「科学を科学以外の目的に利用する最善の方法は…科学をそれ自身の道に進むに任せ(ること)」という教訓→応用研究への支出→基礎研究への支出)。
⑧段落。たしかにこの教訓はもっともらいしが、実際問題として、企業や大学の競争からこうした教訓が得られるものなのだろうか/大学教員が、自分のやりたい研究をしつつ、それへの寄付や補助金を手に入れることができるという、学者にとっていかにも都合のよい制度が、そのように簡単に形成されるものなのか(i)。
⑨段落。こうした制度の形成過程については、上山隆大『アカデミック・キャピタリズムを超えて アメリカの大学と科学研究の現在』の説明が説得的である(j)。上山は、ベン=デービッドが無造作に前提としている「基礎科学──応用科学」という二分法こそが、二〇世紀前半のアメリカにおいて形成され、この二分法が、科学研究への民間資金や公的資金の投入を正当化する「神話」として機能したと言う(k)。(以下、上山の議論の概観~⑩段落)。
⑩段落。アメリカでは、一般の人々は大学における研究や教育にそれほど価値を見ていなかったし、寄付をしてくれる企業家たちは実用的な研究に関心があった(l)。そういう社会的風土の中で、科学研究に資金を集めるために、「純粋な科学研究を行うことの意義を一般大衆に解らせるための物語」として、「ベーシック・サイエンス(基礎研究)」という用語が考え出された/つまり、直接的には社会の役に立つわけではない基礎研究こそが応用研究を準備するので、基礎研究を充実させることは、結局のところ社会の役に立つというわけである(m)。
⑪段落。(ベン=デービッドのいう「教訓」は「神話」だった)。
⑫これが神話だというのは、この主張には実際上の根拠が何もないからだ(n)。
⑬段落。つまり、われわれが「科学」に対して持つイメージそのものが、二〇世紀前半のアメリカにおいて考え出されたということである(o)。
2️⃣ 本文論理構成上の分岐は、⑧段落の2つの疑問文(i)である。そこで筆者は、⑦段落ベン=デービッドの説明、「科学をそれ自身の進む道に任せる」という教訓から応用研究、そして基礎研究への支出が増大したという説明に疑義を呈する。⑦⑧段落より前をA、後をBとすると、Aでは人為的に設立されたアメリカの大学(a)における「学問の自由」の獲得の困難さ(bcd)、その獲得の前提(ef)、そして二〇世紀を越えてやっと、自然科学、社会科学の順でそれが認められたという経緯(gh)が述べられる。
一方Bでは、上山隆大の説に依拠して(j)、「基礎科学──応用科学」という二分法に基づく「神話」が、科学研究への資金投入を正当化したこと(km)が述べられる。そして最後に、その「神話」はわれわれが「科学」について持つイメージともなったという重要な論点が指摘される(o)。これをCとして独立させる。
3️⃣ 2️⃣の本文構成に合わせて、要約文の構成を決める。
A「アメリカの大学は、二〇世紀になっても教師が経営陣に「学問の自由」を求める闘争が続いた(dfg)」。
B「(そんな中で)上山隆大の議論に依ると(j)、基礎科学と応用科学を二分し、前者の充実が後者を準備し社会に有益だ(m)という「神話」が、研究への資金投入を正当化した(k)」。
C「かくして二〇世紀前半に「科学」の一般的イメージが作られた(o)」。
4️⃣ Aについては「学問の自由」獲得の困難さの要因として、大学の設立・運営における、ヨーロッパと比較した場合の私的な性格(大富豪や私企業の寄付で成り立つ)を指摘する(ab)。また、「学問の自由」の遅れを、(e)を利用し「一般市民が憲法によって「言論の自由」を得た後も、「学問の自由」を求める闘争は続いた」と具体的に示すとよい。
Bについては、「神話」が「実用的な研究に関心をもつ寄付者と教育研究に価値を見ない一般人を説得する力となった」と(l)の要素を加えて補強する。Cについては、上述のままだが、本文で「つまり~」だったのを、論理関係に配慮して「かくして(こういうわけで)~」と変更した。
また、ヨーロッパやドイツとの対比(ad)、「自然科学/社会科学」の対比(ch)、「神話」という言葉を使う意図(n)については、主題から外れるので捨象した。
<GV解答例>
主に大富豪の寄付により設立されたアメリカの大学では、市民が憲法上の「言論の自由」を得た後も、教師が経営陣に「学問の自由」を求める闘争が続いた。上山隆大の議論に拠ると、基礎科学と応用科学に二分し、前者の充実が後者を準備し社会に有益だという「神話」の創造が、実用的研究に価値をおく寄付者と教育研究に価値を見ない一般人を説得する力となった。かくして二〇世紀前半に「科学」の一般的イメージが作られたのである。(200)
<参考 S台解答例>
アメリカの大学では設立者の利益に反する主張は許されず、学問の自由は保障されていなかった。こういう社会状況の中、二〇世紀初頭、社会に実利をもたらす応用研究の発展のためには基礎研究の自立性が重要であるという教訓が唱えられ、自然科学研究の自由が実現されていった。しかし、これは自由な研究への資金を獲得したい科学者たちが考え出した神話であり、この神話がわれわれの「科学」に対するイメージを作ることになった。(199)
<参考 K塾解答例>
ヨーロッパの大学では自治や自由が認められていたが、私企業などが設立したアメリカの大学では、特に社会科学の分野で自由が認められてなかった。そこで教員は組合を作って経営陣と闘い、身分が保障される制度を勝ち取った。さらに、自然科学では科学者が基礎科学と応用科学を分け、前者が後者を支え産業に資するという巧妙な言辞を用いて、研究の自由と資金を得た。二〇世紀前半に形成されたこうした科学像は今日でも定着している。(200)
<参考 Yゼミ解答例>
自治の伝統をもつ欧州の大学に比べて、アメリカの大学は設立者である政府や富豪等の支配権が強く、社会科学における学問の自由は二〇世紀初頭まで実現しなかった。これに対し自然科学では学問の自由が早期に実現しており、そこには応用科学の発展には基礎科学の充実こそが重要という、資金提供者を説得するレトリックの存在があった。この主張は実際上の根拠をもたぬ「神話」でありながら、今日の科学のイメージをも形成している。(200)