
沖縄推薦入試の伝説、ついに本格始動! ― 人生が変わる、衝撃の出会い ―
2008年。 沖縄の片隅で、ひとりの生徒が国際基督教大学(ICU)に合格した。その背後には、ある男がいた。GVのパーマこと、大岩。当時、まだ「AO入試」「推薦入試」という制度は、今のように広く知られていなかった。指導の型もない。参考書もない。完全なる未踏の荒野。大岩は、その荒野に最初の道を切り拓いた。
それから約20年。 名古屋大学、九州大学、東京外国語大学、早稲田、慶應、上智、ICU… 数え切れぬ合格者を輩出し、沖縄の推薦入試対策の歴史そのものを創り上げた。
彼は「伝説」と呼ばれるようになった。
今では推薦入試専門の予備校もできた。 「とにかく全員で対応する」というシステム型の塾もある。 情報は増え、ノウハウもマニュアル化されつつある。 だが、問いたい。その講師たちの中に、どれほど「生徒の人生を変えてきた人間」がいるのだろうか?合格させることを最大の目標に掲げる塾は多い。しかし、その合格の先にある「人生」までを見据えて指導している講師は、果たしてどれほどいるのか。残念ながら、そこの対策すらままならず、受験生を不安にさせてしまう場所も少なくない。
推薦入試に挑む者は知っている。 書類作成の難しさを。 面接の重圧を。 小論文で試される「思考の深さ」を。 そのすべてを、大岩は生徒たちとともに乗り越えてきた。 琉球大学医学科の面接前日。 約40名の志望者を一人で相手にし、全員に的確なアドバイスを与え続けた。 「伝説」と呼ばれるゆえんは、まさにこうした瞬間の積み重ねにある。 そして、彼に学んだ生徒たちは口を揃えてこう言う。 「勉強って、こんなに面白いものなんだ!」 「僕って、こんなに面白い人間だったんだ!」 彼はただ合格に導くだけではない。 「人生を変える衝撃」を与えるのだ。
シチズンシップ教育 今年、GVは13年目を迎える。 スタッフもシステムも育ち、大岩自身が推薦指導の第一線から退きつつあった。 しかし。 時代は激動している。 未来は楽観視できない。 そんな時代にこそ、人は「本物の学び」と出会わねばならない。 だから彼は、再び動き出す決意をした。 低学年を対象に開講される「シチズンシップ教育」。 それは単なる推薦対策ではない。 沖縄、日本、世界の未来を担う「エリート」たちへ贈る、覚悟の授業だ。 キーワードは「偶然性」と「想像力」。 社会を深く掘り下げ、自己を揺さぶり、ユーモアを忘れない。 ロックンロールを愛する男が、青春を賭けて叩き込む唯一無二の教育。
「ノウハウを手軽に得たいだけの生徒は他を探せ。 学力を向上させるのは学生の務めだ。 だが、その学力を基礎に社会や自己を深く考察するための知恵と教養を育むのが、講師の腕だ。 GVでは、そこを期待してくれ。」 これは挑発か、それとも本気か。 いや、これこそが大岩の信念だ。
伝説の証 〈国公立大学〉 名古屋大学、九州大学、東京外国語大学、お茶の水女子大学、筑波大学、千葉大学、横浜国立大学、金沢大学、奈良女子大学、広島大学、岡山大学、北九州市立大学、琉球大学… 〈私立大学〉 早稲田、慶應、上智、ICU、MARCH、関関同立… 〈医学科〉 大阪大学、東北大学、名古屋大学、九州大学、千葉大学、新潟大学、福島県立医科大学、岐阜大学、大阪公立大学、広島大学、山口大学、徳島大学、熊本大学、長崎大学、佐賀大学、琉球大学、防衛医科大学校、自治医科大学、国際医療福祉大学、東京医科大学、藤田医科大学、福岡大学、久留米大学… これが「伝説の証」である。
あなたは今、どんな未来を思い描いているだろうか。 合格だけか? 名門大学の肩書きだけか? それとも―― 「自分自身が変わる衝撃」を求めているのか。 もし後者なら、GVで大岩と出会ってほしい。 なぜなら、彼の授業はただの受験対策ではなく、「人生そのものを変える体験」だからだ。 未来は待ってくれない。 チャンスは一度きり。 「伝説」が再び本気を出す、この瞬間に立ち会えるのは、今このページを読んでいるあなただけだ。
⸻ 🔥 今すぐ行動せよ 合格のその先、人生を変える「衝撃」に飛び込め。 沖縄推薦入試の伝説、大岩が待っている。
下記はこれまで大岩が指導してきた生徒の志望理由書・自己PR・課題小論文の一部となっています。ぜひご覧ください。
志望理由①
〇〇大学は建学以来、キリスト教の奉仕の精神と学問的な理性によって、国際的な視野を持ち、社会の構造に切り込み、または地域に根差した活動をすることで、社会の発展や人々の生活の改善に貢献する人材を輩出してきた大学であると理解しています。私はこれまで、私自身に備わった属性、生まれ育った環境、青年期における社会活動を通して、時に苦悩することもありながら、それをも生きるエネルギーに変え、周囲を巻き込み感化していく力を得、それに至上の喜びを感じるようになりました。
〇〇大学への入学が叶えば、日本でもトップレベルの学びの場に置かれ、将来は世界を先導していくに足る知性と人格を備えた学友達に、時に圧倒され、自己の練り直しを迫られることになるでしょう。しかし、私はその挑戦を真っ向から受け止め、自己を絶え間なく成長させることで、「教育で世界を変える」べく教育の平等性と個別性を現場で追究し、その経験を構造の改善に還元できる、そのことで〇〇大学の偉大な伝統に連なり、その名誉を高める存在になりうる、と確信しています。
学びたいこと①
沖縄の「平和」への執念を受け継いできたこと、「教育は世界を変える」という信念を抱いてきたこと、この2つが私の学びの意欲の根底にあります。〇〇大学のキリスト教理念に基づく国際的な社会貢献性は、私の根源に響くものであり、志望するに至りました。
私は〇〇大学の学際的な学びを最大限に活かし、自分の未来に向けてカスタマイズしていきたいです。確実に軸となるのは「教育学」です。万人に届く教育、個々の可能性を最大化する教育を実践していく哲学と手法について、平等性と個別性に寄与するICT教育の応用について追究していきたいです。加えて「開発研究」「平和研究」等学際的なメジャーを通して、ローカルな問題群をグローバルに、またグローバルな問題群をローカルに捉える視点を鍛え、「グローカルな実践者」としての自己を確立していきたいです。
志望理由②
「最初に学問があるのではなく、自分が考えたことが学問になる」(〇〇大学パンフレットより)
日本には本当の意味で人権や平和といった理念が実現していません。いや、日本に限らず、そうした理念を現実に根付かせるために、人類は常に先に進む必要があるはずです。私は、そうした学びや行動に乗り出す上で、未開拓の領域を切り開くことを促す〇〇大学の姿勢に共鳴し、受験を決意しました。
私は沖縄に生まれ、幼い頃より祖父母から沖縄戦の話を聞かされてきました。また部活動で原爆やハンセン病について学び、戦争の記憶を継承する難しさや人間の中に巣食う差別心に向き合ってきました。すべての人の人権が尊重され、誰もが平和を享受できる社会を実現する。今も、それを実現するために人生を賭け活動されている方がいます。私もそうした活動に加わりたいです。ただ、そのためには人権や平和が実現されていない現状を多面的に分析し深層を見抜く力が必要です。その点で「責任ある地球市民を育てる」という理念を掲げ、多様性溢れるキャンパスでリベラルアーツを提供する〇〇大学での学びが必然だと考えました。
学びたいこと②
〇〇大学には魅力的なメジャーが揃っていますが、その中でも「平和研究」を軸にして4年間学んでいきたいと考えています。平和な社会の構築に貢献したいからですが、その際私は国と国との戦争という観点に留まらず、究極的にはすべての人の心が平安である状態として「平和」を捉えたいです。その観点に従えば平和は同時に人権の問題です。「平和研究」の学際的カリキュラムを活用し「人間の安全保障」を実現するための巨視的または微視的なアプローチを追求したいです。
もう一つ、上との関連で愛情や憎悪を生む人の感情のあり方に関心があり、その点では心理学・社会学・教育学なども視野に入りますが、今は「音楽」に傾いています。部活動で琉球や東南アジアの民族舞踊を体感したことにより、音楽の呼び起こす属性を超えた共感作用に興味があるからです。いずれにしろ一年時は先入観を持たず〇〇大学の提供する豊富な学びに貪欲に挑戦し、副専攻を定めたいです。
自己PR(抜粋)①
バレーボールの攻撃は、つまるところ2つしかありません。エースが決めるか(A)、それ以外か(B)です。理想としては、チームが連動して動き、相手ブロックのまだ準備できていないところにスパイクを打つ(B)。訓練されたチームは、ここに強みを持ちます。そうでない場合、お決まりのポイント、つまり味方にも敵にも見え見えのポイントに高くトスをあげます。エースは、できるだけ高く跳び、相手ブロックの待ち構える中、それを打ち抜くように強いスパイクを放つ(A)。チームの勝負強さは、困った時のエースの働きにかかっています。そして、経験の浅い弱小チームは、パターンAに頼るしかないのです。
私は中高6年間、バレー部でエースを務めました。典型的な弱小チームのエースです。しかも内心ビビりな私。私の自信の無さはチームに波及し、勝敗を左右します。それを自覚した私は振る舞いを変えました。失敗などでいちいちくよくよしない。いつも笑顔で仲間を(そして弱気な自分を)叱咤し続ける、チーム1のムードメーカーでいよう。私が率先して行動を変えることで、チームも気持ちが強くなりました。その結果、はじめ4部を彷徨っていたチームは3部で優勝するところまできました。
自己PR(抜粋)②
コップは、形のない液体を汲み取り、固定化し、別の個体(人間)にその液体を媒介する働きをもちます。
私は集団の中で常に「コップ」の役割を担ってきました。とりとめのない集団の声を汲み取り、形にすることで、方向性を示します。今度は、成員がその方向性をいったん「飲み干し」、そこを共通了解とすることで、議題をさらに精密化していきます。(中略)
会議は混迷を極めました。そして、最良の案として最後に「コップ」に掬い取られたのは「軽音部とコラボして、爆音を墨で表現しよう」というものでした。
本番は無事、盛況のうちに終わりました。観客も部員も楽しめたのが何よりでした。会場に来ていた「あの頃の僕」にも「美味しいもの」を手渡せただろうか。形として引き継ぐ、これも「コップ」のリーダーシップです。
課題小論(抜粋)①
ダイバーシティを尊重することは、自分たちと彼らの違いを尊重することだとみなされています。しかし、それは相手をカテゴライズして理解することだけで終わるものであってはなりません。その中にも、また多様でかけがえのない生が存在します。私たちはすでにマジョリティとして自足しています。しかし、例えば自分が女性であることを意識した場合に分かることですが、マイノリティの側からは常に届かない声があります。その声に繊細に耳を澄まし、声にならない声を汲み取ることが大切ではないでしょうか。また、そうして一人一人との対話を欠かさないことによって、「共感の根っこ」が顕れるのではないでしょうか。多様な存在、その中の多様な一人一人との対話を欠かさないことによって、「共感の根っこ」から私の中に多様な要素が流れ込み、私の心が豊かになっていきます。そして、多様性を内在化した「私」と「私」が真の共生社会を構成していきます。私は、ハンセン病回復者の方々との交流を契機に「ダイバーシティ」のあり方をこのように理解するに至りました。
課題小論(抜粋)②
以上、私が English Advance Class で学び劇的に変わった点は、自己と他者と世界に対する見方です。まず自己に対しては、「私でいること」に誇りを持てるようになりました。知らず知らずのうちに周りに合わせることに慣れていた自分に気づき、自己の個性を伸ばし表現することに積極的になりました。次に他者に対しては、無意識のうちに「普通」のヴェールを被せたり、自己の常識の色眼鏡で見ていないか、注意深く接するようになりました。他者が自分と違っていることを恐れるのではなく、違っているからこそ発見があり楽しみがあると思えるようになりました。
そして世界に対しては、critical=批判的なものの見方ができるようになりました。クリティカル・シンキング──日本でもビジネスシーンなどで重用されて久しい言葉です。しかし、その用法はハウツーに限られているように見えます。元の私も含め日本人は、「和」を重んじるあまり(それはウチとソトに分け、ソトを排除することにもつながる)、批判的な立場をとることが苦手なのではないでしょうか。批判的に吟味する、それは物事を前提から掘り起こすことです。それは世界をより美しいものに、innovative に変えていく原動力です。私はそのことに貪欲でありたいです。
課題小論(抜粋)③
とりわけ「自由」が一人歩きすれば強者の論理が働きがちなので、社会の法化によって公正さが追究される必要があります。現在のグローバル化に伴い、先進国と途上国を巻き込んだ国際競争が激化し、日本でも格差拡大が深刻になっています。日本では1990年代末から新自由主義への転換が図られ、規制緩和が叫ばれるようになりました。
本来、法的規制とは自由競争による弊害を最小化するものでもあったはずです(農業、中小企業、労働者、消費者、高齢者や子どもの保護など)。それに対して規制を緩和するということは、もちろん時代に合わなくなった法の変更は必要だとしても、本来法により守られるべき人権が蔑ろにされる危険性を孕みます。その点で、現代において法を学ぶ意義がより大きくなっているのではないでしょうか。
憲法をはじめとした法の体系は、現実の社会に対して我々の目指すべき理念を示します。もちろん現実と理念はすぐに一致するものではありませんが、現実社会が様々な矛盾や不公正を現出させている以上、我々は現実を理念に近づける努力を欠かしてはなりません。ここに現代において法を学ぶ意義があるのではないでしょうか。



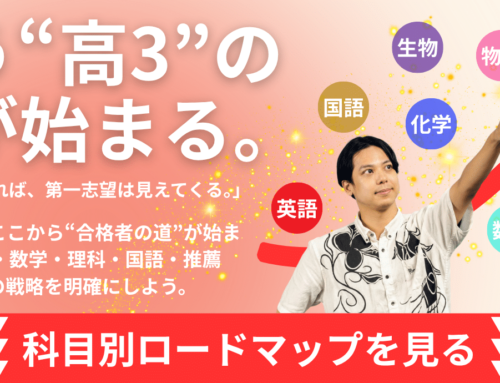

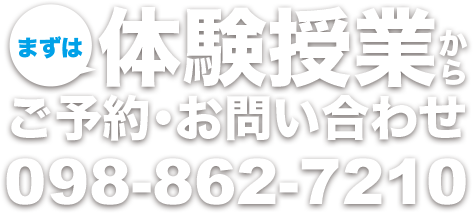

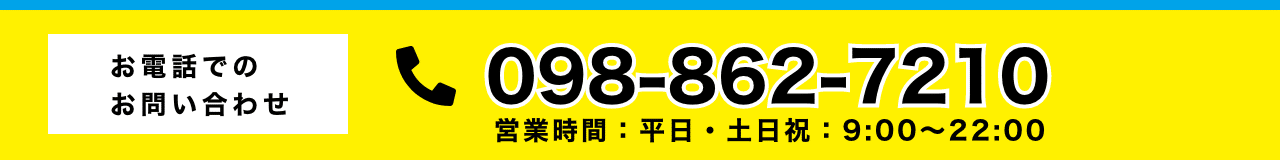


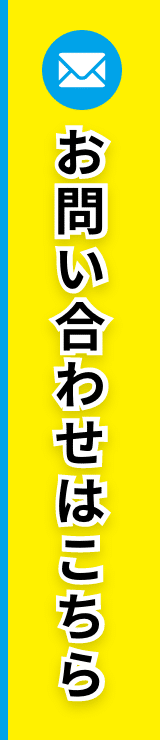
コメントする
You must be logged in to post a comment.