医学科での学生生活について
医学科での生活は、一言でいうと本当に忙しいです。それでも、自分なりに時間の使い方を工夫しながら、部活も続けていますし、友達と遊ぶ時間も取るようにしています。そういったバランスが取れているおかげで、忙しい中にも楽しさや充実感を感じられる学生生活を送れています。
一番大変だった出来事
医学科での生活の中で、これまでで一番きつかったなと感じたのは、部活と2つのバイトを掛け持ちしていた時期に、テスト期間が丸かぶりしてしまったことです。特にその時は、バイト先に「この期間がテスト週間です」と事前に伝え忘れてしまっていたんです。シフトが入っているのに後から「やっぱり減らしてください」と言うのは申し訳ない気がして、結果として通常通りのスケジュールで勤務を続けることにしました。
気づいたときには、すでに3週間にわたる怒涛のテスト期間が始まっていて、本当に「どうしよう」と頭を抱えました。しかも、その中には普段よりも難易度が高く設定されたテストが含まれていて、これまでで一番「限界かもしれない」と思った出来事でした。
それでも、バイトが始まる前に早めに行って、勉強をしたり、隙間時間を有効活用したりして、少しでも前に進めるように心がけました。正直、「気合い」だけで乗り切ったところもあります。
医学科での学びの流れ
医学科での学びは、学年ごとに段階的に進んでいく形になっています。1・2年生の間は、学習の中心は「自分の身体の中で起こっていること」に関する基礎的な内容です。2年の後半から4年前半にかけては、学習の内容が一気に臨床医学へとシフトしていきます。現在は、そうした基礎と臨床の学びの総仕上げとして、「CBT」という試験に向けた勉強を進めているところです。そのため、今は毎週金曜日はいつもより早く来て、勉強する習慣を続けています。
大学生としての生活と工夫
大学に入ってからは、生活が一気に忙しくなりました。それまでの生活では、基本的に「勉強」が中心でしたが、大学では勉強に加えて部活やバイト、さらには友達との遊びの時間も増えてきて、やることの幅が一気に広がります。時間の使い方や優先順位の付け方をしっかり意識していないと、すぐにどれかが疎かになってしまうのが現実です。正直、そのすべてを完璧にこなすのは本当に難しいと感じました。
そんな中で、僕が意識してきたのは「周りと協力する」という姿勢です。医学科のように情報量が多く、常に新しい知識が求められる環境では、仲間との連携が学習の効率を大きく左右します。だからこそ、友人や先輩の力を借りて、時には助けてもらいながら、「一緒に受かる、一緒に乗り越える」ことを大切にしてきました。周囲と支え合いながら進んでいけることは、大学生活の中でも特にありがたいことだと実感しています。
チューターとしての取り組み
GVでチューターとして関わる中で、常に意識しているのは「1人1人の生徒をしっかり見ることの大切さ」です。どんなに忙しくても、生徒一人ひとりの状況や性格、学習の進み具合は異なるので、まずはその子自身に合った声かけや指導ができるように心がけています。
中でも特に大事にしているのが「逆算する視点」です。受験本番は1月・2月と決まっている以上、そこから逆にカレンダーを辿って「じゃあこの時期にはどこまで終わっておく必要があるか?」を明確にしてあげるようにしています。たとえば、10月から演習にしっかり入るためには、7~9月の段階で標準問題までを一通り仕上げておく必要があります。そういったスケジュール感を生徒と一緒に共有しながら、「今のスピードで間に合うかどうか」「調整が必要ならどこをどう変えるか」などを一緒に確認するようにしています。
教え方で意識していること
生徒から質問を受けたとき、僕がまず意識しているのは、ただ一方的に解説を始めるのではなく、「どこから分からなくなっているのか」「どの部分までは理解できているのか」をきちんと聞き取ることです。これは、限られた時間の中で本当に意味のある指導をするためにも、すごく大切なことだと感じています。
たとえば、問題の冒頭でつまずいているのか、それとも途中式までは理解できていて答えの出し方だけが分からないのかで、必要な説明の内容や深さは大きく変わってきます。そこを曖昧にしたまま解説を始めてしまうと、生徒にとっては「もう分かっているところを繰り返される」ことにもなりかねませんし、時間のロスにもなってしまいます。だからこそ、まずは生徒の理解の位置を正確に把握してから、その場に最も適したアプローチで説明するよう心がけています。
また、分からないことを素直に「ここが分かりません」と言える空気をつくることも大切だと思っています。なので、説明している最中でも「今のところ、もし分からなかったら途中で止めていいよ」と声をかけたり、表情や反応から理解度を読み取ろうとしたり、常に双方向のやりとりを意識しています。ただ教えるだけでなく、対話をしながら一緒に学んでいくことが、生徒にとっても自分にとっても一番良い形だと実感しています。
わからないところをその場でしっかり解消すること。それが次の学びへの自信にもつながると信じて、丁寧な対応を大切にしています。
印象に残っている生徒とやりがい
GVでチューターを始めたばかりの1年目、初めて担当した生徒たちのことは、今でも強く印象に残っています。初めて教える立場として関わる中で、実際にその生徒たちがどんどん成長していく姿を間近で見られたことは、僕にとっても大きな経験でした。特に記憶に残っているのは、成績の伸びが本当に目に見えて分かったことです。「なんでこんなに早くできるようになるんだろう」と驚くほどのスピードで成績を上げていく姿には、純粋に感動しました。
もちろん、その背景には彼ら自身の努力があったことは間違いありません。でも、少しでもその成長の過程に自分が関われたのだとしたら、それは本当に嬉しいことです。教えた内容がしっかり身について、それが結果として現れてくる瞬間は、チューターとしてのやりがいを一番感じる場面です。
自身の勉強法の変化
自分の勉強法が大きく変わったのは、現役時代と浪人時代を通して得た気づきがきっかけでした。現役の頃は、正直言って効率の悪い勉強をしていたと思います。たとえば、参考書をいくつも同時に手をつけてしまい、どれも中途半端にしか進まず、結局はどれも仕上がっていないという状態が続いていました。英語に関しても、文法の基礎を飛ばしてひたすら長文を読んで、「なんとなく読めた気になる」ような勉強をしてしまっていたんです。
そうしたやり方では、知識が断片的で、応用問題や模試になると全く対応できないということに、現役時代の終盤でようやく気づきました。そして、その反省をもとに、浪人生活では勉強スタイルを根本から見直しました。まず意識したのは、「基礎を徹底的に固めること」と「1冊をちゃんと終わらせること」です。地道に積み重ねていくスタイルに変えたことで、結果的に成績が安定し、得点力にもつながったと実感しています。
チューターとして日々やっていること
僕がGVでチューターとして日々行っている主な業務は、大きく分けて「勉強計画」「個別指導」「巡回対応」の3つです。中でも特に力を入れているのが、勉強計画の立て方とその運用です。これは、生徒の学力を上げるために欠かせない土台だと感じています。
計画を立てる際には、ただ漠然とゴールを設定するのではなく、具体的な時期を意識しながら逆算してスケジューリングを行います。たとえば、共通テストや二次試験が1月・2月にあるとすると、9月末から10月末までには実戦的な演習にしっかりと入っておく必要があります。そのためには、7月の段階で標準〜応用レベルの問題に触れ始め、夏の間に土台を築く必要がある、というように流れを明確にしながら計画を立てています。
計画を立てた後も、進捗を週ごとにチェックし、生徒との面談で「今どこまで進んでいるのか」「どこに時間がかかっているのか」を具体的に確認します。その上で、必要であれば計画を柔軟に調整し、生徒一人ひとりのペースや理解度に合った指導を心がけています。
GVチューターの魅力
GVのチューターの一番の魅力は、何と言っても生徒との距離の近さだと思います。ただ勉強を教えるだけの存在ではなく、生徒にとって“なんでも話せるお兄ちゃん・お姉ちゃん”的な立ち位置に自然となれていることが、本当に良いところです。
僕自身、受験生だった頃はケンジさんに、わからないところがあると気軽に声をかけて教えてもらっていました。他にも授業の合間や自習中に、質問をメモしておいて先生を見つけたら声をかける――そんなことが自然にできる環境が、GVにはありました。
那覇高校から医学科を目指すみなさんへ
僕自身、もともとくもんに通っていて、その影響で数学が得意でした。得意科目があると、それを軸に全体の点数戦略を立てやすくなるので、本当に心強かったです。医学科受験は、どの教科も高得点が求められる厳しい戦いですが、その中でも「この科目は自信がある」という武器があるだけで、勉強のモチベーションも安定しますし、入試本番でも精神的な支えになります。だからこそ、自分の得意な科目を早いうちに見つけて、それを磨いていくことはとても大切だと思います。
また、那覇高校からGVに通う生徒の多くは、同じ学校の仲間が近くにいると思います。浪人生になったとき、僕自身も同じように周囲の友達と支え合いながら乗り越えてきました。同じ目標を持った仲間が近くにいることは、何よりの心の支えになります。「自分だけじゃない」と思えるだけで、不安や焦りが和らぎ、もう少し頑張ってみようという気持ちになれるんです。
そして、「わからないところは放置せず、すぐ先生に聞く」ことが本当に大事です。僕自身、大岩先生の授業中に線を引いていた箇所の意図が分からなかったときには、授業後に自分で復習して、それでも分からなければ直接先生に聞きに行っていました。そのたびに読み方のコツや考え方を教えていただき、少しずつ理解が深まりました。
受験勉強と今の学びのつながり
現在、9月に控えるCBTに向けて日々勉強を進めていますが、その中で改めて感じているのが、「受験勉強で身につけた学び方は、今の自分にもしっかり生きている」ということです。特に、僕がチューターとして生徒に伝えている「逆算して考えることの大切さ」は、自分自身にも常に問いかけるようにしています。
CBTのような大きな試験では、一夜漬けではどうにもならない範囲とボリュームがあります。だからこそ、1ヶ月後、2ヶ月後にどのレベルに達しておくべきかを逆算し、今この瞬間に何をすべきかを明確にして行動しなければなりません。今は生徒に「こうした方がいいよ」とアドバイスする立場ですが、同時に自分自身にもその言葉を向けながら、「本当にこのままで間に合うのか」「今やるべきことは何か」と自問自答しながら学んでいます。


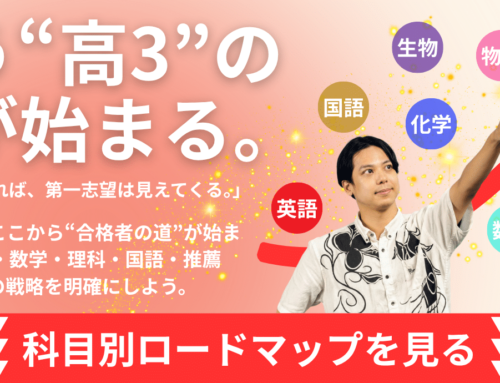

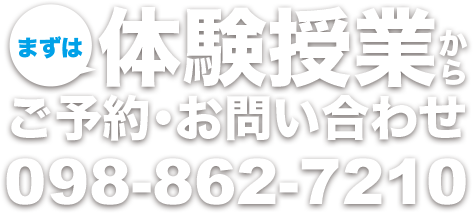

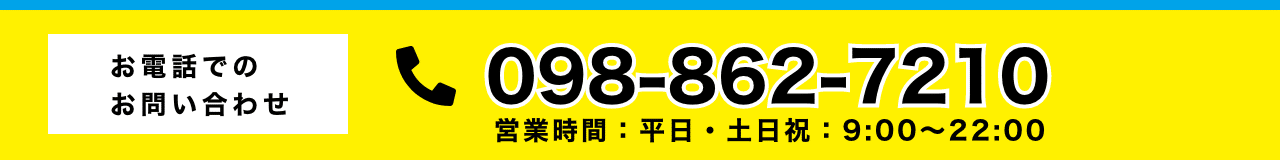


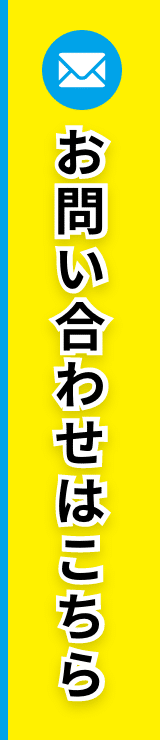
コメントする
You must be logged in to post a comment.