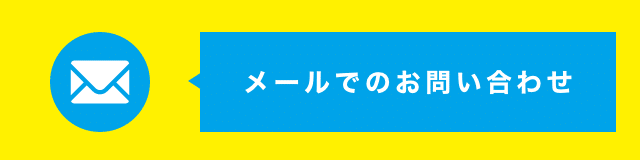目次
- 〈本文理解〉
- 問一 (漢字の書き取り)
- 問二「言葉とそれが意味するもののあいだに空く隙間」(傍線部(1))とある。ここでの「隙間」について、筆者の体験にもとづいて具体的に説明せよ。(2行)
- 問三「自然の装置」(傍線部(2))とある。これと最も近い意味で使われているものを波線部ア〜エの中から一つ選び、記号で答えよ。
- 問四「おなじこと」(傍線部(3))とある。これはどのようなことを指しているか。直前の四角で囲んだ文章中から抜き出せ。
- 問五「ふるまいそのものが変換される」(傍線部(4))とある。このことを、本文中の具体例を挙げながら説明せよ。(2行)
- 問六「顔は人の内面にある特定の感情を表現しているのではない」(傍線部(5))とある。人は他者の「顔(表情)」と「感情」の関係をどのように理解すると筆者は考えているか。「規則」という語を用いて60字以内で説明せよ。
- 問七「言語の意味以上のもの」(傍線部(6))とある。これとほぼ同じ内容を表している部分を本文中から20字で抜き出せ。
- 問八「わたしたちの日々の語らいにはこうしたずれ、あるいは行き違いが頻繁に見いだされる」(傍線部(6))とある。わたしたちの日々の語らいにおいて「ずれ」や「行き違い」が生じるのはなぜだと考えられるか。「テクスト」と「テクスチュア」という二つの語を用いて100字以内で説明せよ。
〈本文理解〉
出典は鷲田清一『つかふ──使用論ノート』。
①段落。他者との交通が生まれるとき、そのもっとも基礎的な媒体となるのは言語である。「ことばづかい」という語もあるように、言葉もまた使われるものである。言葉とはしかし、どういう意味で「使われる」と言われるのか。
②段落。哲学の研究者としてまだ駆け出しの頃、言葉についてつくづく考えさせられた思い出が私にはある。
③段落。…
④段落。「珠々」と名づけた九官鳥の、元はといえばセキセイインコの産卵用の大きな巣箱を水洗いするために、彼を別の小さな竹の巣箱に移すべく捕らえようとしたら、なんと、激しく逃げ惑いながら「おはよう、おはよう」と叫ぶのである。‥‥面食らった。それまで私が「珠々」に教えた語はただ一つ、この「おはよう」だった。それ以外にも、「珠々」は、これは勝手に二語を憶えていた。(「はーい」「ママ、おしっこー」)。…その「珠々」がおのれの恐怖を「おはよう」と、しかも私の声音に似たそれで表出したのである。これには虚をつかれた。虚というのは、不意ということでもあるが、同時に「言葉とそれが意味するもののあいだに空く隙間」(傍線部(1))という意味でもある。そのことについてかつて私は以下のように書いた。
〈恐怖と「おはよう」、もしこの結びつきが変だとしたら、恐怖と「こわい」の結びつきもやはり変である。「こわい」という私たちの感情と「こ・わ・い」という発声のあいだには、どんな必然的な連関も、どんな類似性も存在しないからだ。そのかぎりで、私たちがこわいときに「こわい」と言うのと、ジュジュがこわがって「おはよう」と叫んだことのあいだには何の違いもない。私たちもまた「自然の」声を失って、特定の言語という制度のなかでしか自己を音声的に表出しえなくなっているからである。怯えているとき、指を切ったとき、火傷をしたとき、私たちはギャーと叫ばないで、身体をこわばらせつつ、とっさに「こわい」「痛い」「熱い」と金切り声を上げるのである。それ以外にも別の表現がありえたかもしれない、ということに想像がおよばなくなっているのである。『ファッションという装置』〉
⑤段落。九官鳥としての「自然の装置」(傍線部(2))として「殊々」がもって生まれたその表現媒体は、このとき、みずからを廃棄して、すっかり別の装置に置き換えられていた。「おなじこと」(傍線部(3))はヒトであるわたしたち自身にも言えるはずだと、「殊々」のふるまいから諭されたのである。
⑥段落。「ことばをつかう」とひとは言う。このとき「つかう」というのは、言語を表現の道具として、あるいは伝達の手段として使用しているということなのだろうか。
⑦段落。たとえば「痛い!」。この語を発するとき、わたしたちはじぶんが感じている痛みを他者に伝えるべく描写したり、表現したりしているのだろうか。そんなはずはなかろう。そんな思いと表現との隙間なしに、この語でもってじぶんの痛みをじかに他者に訴えているはずである。それは描写や記述ではなく、痛みの表出そのものである。
⑧段落。〈ヴィトゲンシュタインの引用〉。
⑨段落。ここで痛みの言語的表出は痛みの自然的表出にとって代わっているのだと、ヴィトゲンシュタインはいう。彼によれば、言語は私たちの思考や感情、あるいはイメージの記号でもなければ標識でもない。…呻くこと、顔をしかめること、力むこと。これが痛みの原初的表出とするなら、「[わたしは]痛い」もまたそれに準ずる痛みのふるまいそのものだというのである。それは痛みの記号でもなければ、痛みを記述する文なのでもない。むしろ痛みのふるまいそのものだというのである。
⑩段落。「殊々」がそうであったように、わたしたちもまた言葉を憶えることによって、以後、「痛い」「熱い」「あっちっち」と言うが、「ぐーっ」と唸ったり、「ぎゃー」と叫んだりしえなくなる。自然的発声を失って、言語で唸り、叫ぶほかなくなるのだ。「ふるまいそのものが変換される」(傍線部(4))。…わたしたちは感情の表出もまた言語という網の目をとおしてしか表出できなくなったのである。自然的なもののこの変換こそ、わたしたちが「文化」と呼び習わしてきたものにほかならない。
⑪段落。ほぼ時をおなじくして現象学者、メルロ=ポンティもフランスで考えていた。痛みや怒りの所作は、それらの記述でも表現でもなく、痛みや怒りそのものなのだと。〈メルロ=ポンティの引用〉〜⑫段落。
⑬段落。メルロ=ポンティのこうした考えと、ヴィトゲンシュタインのそれとにはいくつか共通するものがある。
⑭段落。いうまでもなくまずは、言語というものを、思考や感情を他者に伝える道具や手段としてではなく、人のふるまいの一つとみなすという点である。…
⑮段落。次に、そうしたふるまいとしての言語が人間における自然的なものの変換としてとらえられていることである。ヴィトゲンシュタインは言語を自然的表出に「とって代わる」ものとしたが、メルロ=ポンティはさらに言語への変換のその恣意性に着目して、次のように言う。〈…感情や情念的な行為も、語とおなじように作り出されたものだ。…人体のなかにすでに刻み込まれてしまっているようにみえる感情でさえも、本当は制度なのだ〉。
⑯段落。ふたたびヴィトゲンシュタインに戻ると、彼の頻用するGebrauchという概念がこれに呼応する。Gebrauchとは「使用」とか「用法」「慣用」とかを意味するドイツ語で、ヴィトゲンシュタインは、語の意味とはほかならぬそのGebrauchのことだというのである。そして、語の意味を知ろうとすれば、その語が人びとの会話のなかでどのように使われているかを知ればよい。…つまり、「痛い」という語は…他者のふるまいをじかに意味するものだということである。人それぞれの感情や思いが一致したところにその語が成り立つのではなく、むしろ「生活形式の一致」においてこそそれは成り立つとするのである。
⑰段落。あるいはここで、言葉とともに、顔もしくは表情というものを思いおこしてもよい。「顔は人の内面にある特定の感情を表現しているのではない」(傍線部(5))。いいかえると、顔をとおしてその背後にある何らかの感情を読み取るようなものではない。目の前にある顔もしくは表情がいってみれば感情として現前している、つまりひとは感情そのものとして他者の顔に向きあうのだ。ただ、それに向きあうにも特定の規則がある。どういう感情がどういうものとして受けとられるか、読み取られるかは、それぞれの文化が内蔵しているそれぞれの「生活形式」としてあるということである。そしてそこにメルロ=ポンティのいう恣意性の理由が見いだされる。
⑱段落。そこで言葉づかいである。言葉ではなく言葉づかいとことさら言うときには、これまで述べてきたような「言語の意味以上のもの」(傍線部(6))が含意されている。それは言葉の肌理(テクスチュア)とでもいうべきものである。言葉はいわば回転扉をなす。〈意味〉としての言葉と〈肌理〉としての言葉という二重の姿である。これをテクストとしての言葉とテクスチュアとしての言葉というふうに言い換えることもできる。…そして私たちはある人の言葉づかいをして「荒い」とか「丁重だ」とか「品がない」とか言う。それはある人の言葉を言葉として受けとる側の感触を表している。つまり「つかい」ということで言葉の肌理のありようをいっているのである。
⑲段落。みずからが語り、他者が受けとるこの言葉の肌理を知らない、あるいはあえてそれに耳を塞ぐ言語行為の典型がヘイト・スピーチなるものであろう。…他者の言葉を聴くときも同様である。私たちはテクストとしての他者の言葉をしかと受けとめても、テクスチュアとしての他者の言葉を聞きそびれることがしばしばある。そのとき、他者はじぶんの言葉は字面は理解されても、言葉じたいは逸らされたと感じるだろう。ヘイト・スピーチほど激烈ではなくとも、「わたしたちの日々の語らいにはこうしたずれ、あるいは行き違いが頻繁に見いだされる」(傍線部(7))。
問一 (漢字の書き取り)
a.潜 b.連関 c.廃棄 d.習俗
問二「言葉とそれが意味するもののあいだに空く隙間」(傍線部(1))とある。ここでの「隙間」について、筆者の体験にもとづいて具体的に説明せよ。(2行)
内容説明問題。筆者の体験とは、筆者の飼っていた九官鳥が恐怖を「おはよう」と表出したことである。傍線直後、かつて筆者の書いた文章による説明に従うと、恐怖と「おはよう」の結びつきが変なのと同様、それを「こわい」と発声したところで、両者の間に必然的連関も類似性も存在しないということになる。その状態と言葉の結びつきの恣意性を筆者は「隙間」と言うのである。以上より、「筆者の飼う九官鳥が恐怖の状態を「おはよう」と叫んだのと同様/それを「こわい」と表現しても/両者の間に類似性がないこと」と解答できる。「類似性」を、同じく本文中の「必然的連関」に代えてもよいだろう。
〈GV解答例〉
筆者の飼う九官鳥が恐怖の状態を「おはよう」と叫んだのと同様、それを「こわい」と表現しても、両者の間には類似性がないこと。(60)
〈参考 K塾解答例〉
恐怖を感じた九官鳥が「おはよう、おはよう」と叫ぶように、言葉が普通の意味とは異なる使われ方をされていること。(54)
問三「自然の装置」(傍線部(2))とある。これと最も近い意味で使われているものを波線部ア〜エの中から一つ選び、記号で答えよ。
〈答〉エ (原初的表出)
問四「おなじこと」(傍線部(3))とある。これはどのようなことを指しているか。直前の四角で囲んだ文章中から抜き出せ。
〈答〉
「自然」の声を失って、特定の言語という制度のなかでしか自己を音声的に表出しえなくかっている(こと)
問五「ふるまいそのものが変換される」(傍線部(4))とある。このことを、本文中の具体例を挙げながら説明せよ。(2行)
内容説明問題。傍線部の「変換」は、前文「自然的発声を失って、言語で唸り、叫ぶほかなくなるのだ」を言い換えたものである。そして「のだ」で結ぶ前文も、その前文(傍線部の前々文)の具体的記述を抽象的に換言したものである。ならば傍線部の「変換」とは、「ぐーっ」「ぎゃー」といった痛みに即した自然的発声が「痛い」「熱い」「あっちっち」といった言語表現に変わることである。
では、筆者はなぜそれを「ふるまいそのもの」の変換と言うのか。手がかりになるのは前⑨段、ヴィトゲンシュタインに依拠した説明。特に後ろの三文、「痛い」は痛みの記号でも痛みを記述する文でもなく、痛みのふるまいそのものだ、という内容。言うまでもなく「記号」とは「意味を伝えるもの」である。その記号性を否定した上で「ふるまいそのもの」とするのは、痛みに即した「ぐーっ」などの自然的発声と同様、痛みと「いたい」という音声表出の間にも意味は介在しない、ということではなかろうか。以上の理解により、「痛みに即して「ぐーっ」の代わりに「いたい」と表出するように/ある状態に即して表出される音声が/意味を介在せずに変わること」と解答できる。
〈GV解答例〉
痛みに即して「ぐーっ」の代わりに「いたい」と表出するように、ある状態に即して表出される音声が意味を介在せずに変わること。(60)
〈参考 K塾解答例〉
痛みを感じて「ぎゃーっ」と叫ぶことが、言葉を覚えることで「痛い」という言葉で叫ぶほかなくなるように、自然的発声が言語的表出に置き換えられること。(72)
問六「顔は人の内面にある特定の感情を表現しているのではない」(傍線部(5))とある。人は他者の「顔(表情)」と「感情」の関係をどのように理解すると筆者は考えているか。「規則」という語を用いて60字以内で説明せよ。
内容説明問題。「顔(表情)」と「感情」の話題は⑰段落で独立完結しており、よって当段落のみで解答を構成するとよい。当段落の内容は以下の通り。顔(表情)は感情の現前である→感情は規則=文化の内蔵している「生活形式」により読み取られる→よってその「表情一規則一感情」(※「感情一規則一表情」ではない!)は恣意性を免れない(メルロ=ポンティ)。以上の理解から、「顔(表情)」と「感情」の関係を「規則」を用いてまとめると、「自らが帰属する文化に内蔵する生活形式を共有し/そこから導かれる規則に照合させて/他者の表情から直接的に感情を理解する」となる。
〈GV解答例〉
自らが帰属する文化に内蔵される生活形式を共有し、そこから導かれる規則に照合させて、他者の表情から直接的に感情を理解する。(60)
〈参考 K塾解答例〉
他者の顔の表情そのものを、それぞれの文化が内蔵している特定の規則を通じて、感情の現前したものとして理解している。(56)
問七「言語の意味以上のもの」(傍線部(6))とある。これとほぼ同じ内容を表している部分を本文中から20字で抜き出せ。
〈答〉
ある人の言葉を言葉として受けとる側の感触
問八「わたしたちの日々の語らいにはこうしたずれ、あるいは行き違いが頻繁に見いだされる」(傍線部(6))とある。わたしたちの日々の語らいにおいて「ずれ」や「行き違い」が生じるのはなぜだと考えられるか。「テクスト」と「テクスチュア」という二つの語を用いて100字以内で説明せよ。
理由説明問題。傍線部は本文末文。本文冒頭で提示された「ことばづかい」についての問い(主題の提示)に対する答えにあたる最終の二段落(⑱⑲)が主な解答範囲となる。内容は以下の通り。言葉には〈意味〉=テクストとしての言葉と〈肌理〉=感触=テクスチュアとしての言葉の二重の姿がある(⑱)→語り手、もしくは聞き手がテクスチュアの面を十分に配慮しない場合がある(⑲)→日々の語らいにずれや行き違いが見いだされる(傍線部)。
これに加えて、前段(⑯⑰)からのつながりを意識する(⑱段落は「そこで」で始まる)。特に「「生活形式の一致」においてこそそれ(=言葉)は成り立つ(⑯)/どういう表情がどういうものとして受けとられるか、読み取られるかは、それぞれの文化が内蔵しているそれぞれの「生活形式」としてある(⑰)」に着目するとよい。つまり「生活形式の一致」が言葉が共有されるための条件であり、その違いも「ずれ」や「行き違い」をもたらしうる。そして「生活形式」の違いは、言葉の一般的な意味では捉えることのできない〈肌理〉に関わるものであろう(自明)、ということである。この理解を踏まえ、「言葉には、一般的な意味を伝えるテクストとしての側面に加えて/生活形式の違いを反映し/感触を伝えるテクスチュアとしての側面があるのに/後者を十分に配慮せずに/言葉を伝え、また受けとろうとするから」(→ずれや行き違いが生じる)と解答できる。
〈GV解答例〉
言葉には、一般的な意味を伝えるテクストとしての側面に加えて、生活形式の違いを反映し、感触を伝えるテクスチュアとしての側面があるのに、後者を十分に配慮せずに、言葉を伝え、また言葉を受けとろうとするから。(100)
〈参考 K塾解答例〉
言葉には意味を伝えるテクストとしての言葉と感触を伝えるテクスチュアとしての言葉の二重性があり、語る者も聞く者も、テクストとしての側面に注目し、テクスチュアとしての側面をしばしば見失いがちだから。(97)