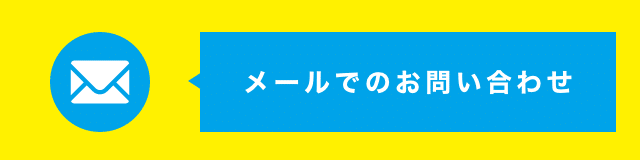目次
- 〈本文理解〉
- 〈設問解説〉問一 「こうした思考法」(傍線部A)とは、どのような思考法をいうのか。本文中から抜き出して三〇字以内で答えよ。
- 問二 「それだけが具備すれば残りの排列はどうでもいい」とあるが、なぜか。その理由を三〇字以内で述べよ。
- 問三 「方法としてのアナロジー(類推)」(傍線部C)とは、具体的にはどのような方法をいうのか。本文中の言葉を用いて五〇字以内で説明せよ。
- 問四 「この世界をどのように見、どのように考えたらいいのかというヒントが満載である」(傍線部D)とあるが、その例として作者はどのような例を挙げているか。五〇字以内で説明せよ。
- 問五 「ようやく時代が寺田寅彦に追いついてきた」(傍線部E)とあるが、それは具体的にはどのようなことか。本文全体の論旨を踏まえ、八〇字以内で説明せよ。
〈本文理解〉
出典は千葉俊二『文学のなかの科学 なぜ飛行機は「僕」の頭の上を通ったのか』。
①段落。寺田寅彦はラフカディオ・ハーンの説を引いて、祖先を千年前にさかのぼると、現在の自分は二〇〇〇万人の血を受け継いでいる勘定になるといっている。…どうやら寅彦は桁数をひとつ間違えたようだが、「過去」の経験を数えきれぬ祖先から受け継いでいるという考えは、寅彦の記憶に強烈なインパクトを与えたようである。
②段落。が、それ以上に「こうした思考法」(傍線部A)は、寅彦の関心を「自分」というものの成り立ちや存立の根拠といったことへ向けさせ、「なんだか独立な自分というものは微塵に崩壊してしまって、ただの無数の過去の精霊が五体の細胞と血球の中にうごめいているという事になりそうであった」と記している。似ておりながら少しずつ違う何枚もの自画像を描きつづけるということは、自分が何世代にもわたる先祖の血を受け継いでいるという時間軸を、表情の変化という空間軸に置き換えることでもある。
③段落。微妙に違った自画像を何枚も重ね合わせ、それらに共通しているところに「自分」というものが存在するのだろうか。そうした「自分」は、どこまでいっても見つけることは不可能である。寅彦は「仕上がるという事のない自然の対象を捕えて仕上げることが出来るとすれば、そこには何か手品の種がありそうである」という。考えてみれば、あらゆる学問はこの「手品」の種明かしに終始しているわけで、寅彦随筆の魅力も日常的に私たちがとらわれて気づかずにいるさまざまな「手品」の在りかを指し示し、その種明かしを披露してくれるところにある。
④段落。たとえば、私たちが人の顔を見ているときに頭のなかに結ぶ像は、「相似」を決定するための少数の主要な項目の組み合わせであって、「それだけが具備すれば残りの排列はどうでもいい」(傍線部B)。それは満天の星空に星を適当な線で結びながらいろいろな星座をつくって、星の位置を覚えることに似ている。「顔の相似」という不思議な現象を追いかけて、結局、寅彦は「(学問は)事物の真を探求するとは云うものの…物の本来の面目はやはり分からないで、つまりは一種の人相書…を描いている場合も多いように思われるが、そのような不完全な「像」が非常に人間に役に立って今日の文明を築き上げた」のだと、ひとつの見事な手品の種明かしをおこなっている。
⑤段落。「相似」──似ているものを対比すること、類似したものを共通項としてカッコでくくることで、私たちは混沌として見透かしのきかない現実を少しずつでも整理することができ、バラバラに生起する現象をわずかにでも秩序立てて見ることができる。寅彦の随筆はこうした相似を次々と列挙するところからはじまるが、これはあらゆる学問の要諦でもあろう。寅彦はそれを自覚的、意識的に駆使し、いわば「方法としてのアナロジー(類推)」(傍線部C)をひとつの思考の武器としてそれらの膨大な随筆群を書き上げていったといえる。
⑥段落。「厄年とetc.」は、今日ならばビッグデータの対象として扱われるような問題を、コンピュータもなしに考えようとした試みである。胃潰瘍で入院したのが、ちょうど四十二歳の厄年ということもあって、この文章が書かれたのだろうけれど、「厄年」の意味を知るためには、自分の過去の一切のものを「現在の鍋」にぶち込まなければならないという。これは現在の「自分」が何世代にもわたる数知れない先祖の血を受け継いだ存在だという「自画像」で語られた思考と同工異曲である。…
⑦段落。すべてはフラクタル(自己相似性)な構造をもち、カオス理論において論ずることも可能であろう。書物にしても例外ではなく、「「六国史」を読んでいると現代に起こっていると全く同じことがただ少しばかりちがった着物の名前を着て古い昔に起こっていたことを知」るといい、「古い事ほど新しく、一番古いことが結局一番新しいような気がして来る」といっている(「読書の今昔」)。寅彦の思考の根底には、故きを温ねて新しきを知るという温故知新の考えが横たわっており、温故知新ということは思考上のフラクタルといって差し支えない。
⑧段落。寅彦の文章はどれひとつとってみても、今日なお新鮮で、示唆に富んでいる。「この世界をどのように見、どのように考えたらいいのかというヒントが満載である」(傍線部D)。寅彦の文章に触れることで、自然を見る眼が大きく変えられるし、ぼんやりした視野がとても見晴らしのよいものとなる。二〇一一年の東日本大震災の折には新聞、雑誌、テレビなどのメディアに「天災は忘れた頃にやって来る」「正しく恐れる」など寅彦の言葉があふれたことは記憶に新しく、まさに温故知新をそのままに体したといえる。
⑨段落。寅彦は物理学者として自然科学を深く学び、その眼をもって森羅万象みずからの言葉で語りだしている。時に科学的な専門用語が用いられたとしても決して難しいことはなく、平易な言葉で言い直されて誰にでも分かりやすく丁寧に解説されている。二〇世紀の後半にはコンピュータの発明により、自然科学の発展にはめざましいものがあったが、寅彦の文章はちっとも古びていない。それは寅彦が関心を寄せた領域が、コンピュータの進化とともに切り拓かれた分野と重なるもので、寅彦がそのすぐれた直感力でとらえたことの正しさがいよいよ実証され、寅彦の先見性がいよいよ輝きを増しているからである。
⑩段落。寅彦の時代には同じ自然科学でも物理学と生物学は結びつくものではなかった。「もし物理学上の統計的異同の研究が今後次第に進歩して行けばこの方面から意外の鍵が授けられて物質と生命との間に橋を架ける日が到来するかもしれないという空想が起る」(「備忘録」)といっているが、今日ではそれは「空想」ではなく、両者の協力なくして何ひとつ新しい研究分野を切り拓くことができなくなっている。それは心理学などでも同様のことが起こっており、一見もっともかけ離れていると見なされる文学の分野でも同じメカニズムが働いていることが了解されつつある。「ようやく時代が寺田寅彦に追いついてきた」(傍線部E)ような感がある。
〈設問解説〉問一 「こうした思考法」(傍線部A)とは、どのような思考法をいうのか。本文中から抜き出して三〇字以内で答えよ。
<答>「過去」の経験を数えきれぬ祖先から受け継いでいるという考え
問二 「それだけが具備すれば残りの排列はどうでもいい」とあるが、なぜか。その理由を三〇字以内で述べよ。
理由説明問題。傍線冒頭の「それ」が承ける、「私たちが人の顔を見ているときに頭のなかに結ぶ像は、「相似」を決定するための少数の主要な項目の組み合わせであって」が直接的な解答根拠になる。ここから、「少数の主要な項目の組み合わせだけで/顔の「相似」が認識できるから(X)」と解答の核ができる。ここでの「相似」とは、②段落より、時間軸および空間軸において無限のバリエーションをもちながらも「自分」であるということである。この理解に基づき、Xを「その顔の同一性が維持されるから」と言い換えた。これなら傍線の直後の例、星座を結び星の位置を覚える、という内容とも対応する。
<GV解答例>
主要項目の組み合わせだけで、その顔の同一性が維持されるから。(30)
<参考 S台解答例>
真の像でなくても、人の顔は主要な項目だけで認識できるから。(29)
<参考 K塾解答例>
少数の要素の組み合わせだけで、顔の像が生じ相似が決まるから。(30)
問三 「方法としてのアナロジー(類推)」(傍線部C)とは、具体的にはどのような方法をいうのか。本文中の言葉を用いて五〇字以内で説明せよ。
内容説明問題。寅彦が自覚的、意識的に駆使した「方法としてのアナロジー(類推)」(C)を、「本文中の言葉を用いて」説明する。根拠になるのは、同じ段落(⑤)の冒頭「「相似」──似ているものを対比すること、類似したものを共通項としてカッコでくくることで(X)/混沌として見透しのきかない現実を少しでも整理することができ…バラバラに生起する現象をわずかにでも秩序立てて見ることができる(Y)」。ここでYという目的に対し、XがCに相応する方法である。Xは、似ているものを比べて類似性を適用するという意味で、「アナロジー(類推)」の語義にも適う。方法は、目的に即してあるので、「Yのために/Xする方法」という構文で解答する。
以上より、「本文の言葉を用い」て、Y「見透しのきかない現実を整理する」、X「バラバラに生起する事象から類似したものを取り上げまとめる」とした。もとのXにある「共通項としてカッコでくくる」は比喩的な表現なので、そのまま使うのを避けた。
<GV解答例>
見透しのきかない現実を整理するために、バラバラに生起する事象から類似したものを取り上げまとめる方法。(50)
<参考 S台解答例>
バラバラに生起する混沌とした現象を、類似性を共通項として秩序立てて整理し理解への見透しを立てる方法。(50)
<参考 K塾解答例>
「厄年」の随想に見られる、バラバラに生起する現象から、類似したものを共通項としてカッコでくくる方法。(50)
問四 「この世界をどのように見、どのように考えたらいいのかというヒントが満載である」(傍線部D)とあるが、その例として作者はどのような例を挙げているか。五〇字以内で説明せよ。
内容説明問題。寅彦の文章に見られる世界の見方へのヒントの「例」を挙げるように要求している。例ということで同じ段落(⑧)の、「天災は忘れた頃にやって来る」(X1)「正しく恐れる」(X2)の2つを列挙するのは安易ではなかろうか。具体例の「次元」に配慮しなければならない。X1、X2を承けて「まさに温故知新をそのまま体した」と述べていることに着目する。「温故知新」については、前⑦段落でも「寅彦の思考の根底には、故きを温ねて、新しきを知るという温故知新の考えが横たわっており」としているように、⑦⑧段落を通してのテーマになっている。この「温故知新」(Y)が、寅彦の文章に見られる世界の見方へのヒント(D)の直接の例になっている。つまり、Dの例がYであり、さらにその例がXなのである。ならば、解答の中核にはYを置いた上で、「X1X2のようなY」とまとめることもできる。しかし、ここではY「温故知新」について詳しく説明した方が内容は濃くなるだろう。⑦段落、「「六国史」を読んでいると現代に起こっていると全く同じことがただ少しばかりちがった着物の名前を着て古い昔に起こっていたことを知(る)」という寅彦の引用を踏まえ、「歴史の中に現代起こっている事象と類似の事象を見出し/古いことから新しいことを学ぶ温故知新のあり方」とまとめられる。
<GV解答例>
歴史の中に現代に起こっている事象と類似の事象を見出し、古いことから新しいことを学ぶ温故知新のあり方。(50)
<参考 S台解答例>
東日本大震災で、「天災は忘れた頃にやって来る」「正しく恐れる」など寅彦の言葉をメディアが報じたこと。(50)
<参考 K塾解答例>
「天災は忘れた頃にやって来る」「正しく恐れる」や「一番古いことが結局一番新しい」など、温故知新の例。(50)
問五 「ようやく時代が寺田寅彦に追いついてきた」(傍線部E)とあるが、それは具体的にはどのようなことか。本文全体の論旨を踏まえ、八〇字以内で説明せよ。
内容説明問題(主旨)。「寺田寅彦」(X)と「時代=現代」(Y)の類比と捉え、「YはXに先取りされていた」とまとめればよい。Yは傍線のある⑩段落、ここで方向性を決め、⑨段落のXの記述と比べながら双方を具体化していく。⑩段より、現代は自然科学のうち、物理学と生物学の「両者の協力なくして何ひとつ新しい研究分野を切り拓くことができなくなってい」て、このことは心理学や文学にも通じる、と把握できる。物理学と生物学の架橋については寺田が「空想」していたことでもある(⑩)。ここから、Y(∽X)の骨格を「現代は学問の領域を横断する研究が見られる時代」(Y+)と定める。
一方、Xについては、⑨段落冒頭「寅彦は物理学者として自然科学を深く学び、その眼をもって森羅万象みずからの言葉で語りだしている」(X+)が根拠になる。このX+とY+の類比を軸に、「寅彦が関心を寄せた領域が、コンピュータの進化とともに切り拓かれた分野と重なるもので」(⑨)、寅彦の「相似」への着眼を説明した⑤段までの内容を承けた「「厄年とetc.」は、今日ならばビッグデータの対象として扱われるような問題を、コンピュータもなしに考えようとした試み」(⑥)を根拠に加える。以上より、Y「ビッグデータを処理するコンピュータの進化で分野横断的な研究が見られる現状」、X「相似性に着目し物理学者として森羅万象を語った寺田」とし、はじめの構文に組みこむ。
<GV解答例>
ビッグデータを処理するコンピュータの進化で分野横断的な研究が見られる現状は、相似性に着目し、物理学者として森羅万象を語った寺田により先取りされていたということ。(80)
<参考 S台解答例>
対象に類似性を見出す寅彦が、コンピュータの可能にする領域や、物理学と生物学の結びつきなどという新しい研究分野が開拓されることを直観的に先見していたということ。(79)
<参考 K塾解答例>
一見異なるように見える多様な事象に類似性を見出した寅彦は、コンピューターによる統計が進化し、相容れない学問分野が結ばれつつある現代を予見していたということ。(78)